いのちの水 2025年 4月号 第770号
|
わが魂よ、なぜ打ち沈むのか。 なぜうめいているのか。 神を待ち望め。(詩編43の5) 主よ、あなたの慈しみは天にあり、 その真実は雲にまで及ぶ。(詩編36の6) |
目次
|
・地上では途切れ途切れであってもー ブラウニングの詩より |
|
|
・心に残った御言葉 加藤久仁子、 |
・心に残った御言葉
林晴美 |
|
・お知らせ 近畿無教会集会 |
集会だより |
だれでも、日々さまざまの重荷がある。それは小さな子供のときからはじまり、多数の子供たちが、学校にいけずに自宅に一人引きこもってしまう状況が増えつつある。
以前は引きこもりというと児童生徒といった人たちのことを連想していたが、近年は、大人であっても、引きこもる人たちが増加して、最近のデータでは、 15歳から64歳の年齢層では、
約150万人もの人たちが、ひきこもりという。
そのような状況は、それぞれの人たちが、学校や社会のなかで、何らかの圧迫、いじめ、仕事などの重荷を負っていてそれが苦しくて人のなかに入っていけない、
ということなどがあると考えられる。
たとえ家族であっても、その重荷のことを打ち明けることができない、だれにも言えない、それゆえに自室にこもってしまう。
他方、自宅ひきこもりでなくとも、他者に対して決して心のうちを打ち明ける人がいないということも多い。
いくら表面的に友人や同僚と話していても、心は一人で重荷を人知れず苦しむということもある。
そうしたあらゆる状況にあって、ただ愛の神だけは、私たちの心の苦しみや悲しみ、孤独といったものを打ち明けてもきいてくださる。
日々、重荷を負っている私たちそのものを担ってくださるという実感はすでに数千年前から聖書では記されている。
…主をたたえよ
日々、わたしたちを担い、救われる神を。
この神はわたしたちの神、救いの御業の神
主 、死から解き放つ神。 (詩篇68の20~21)
私たちの日々は、さまざまの問題が生じてくる。子どものとき、元気にあふれていてこの世の闇を知らないとき、あるいは成人してからも特別な事故や病気、職業上でも困難など起こらない限り、自分の力で生きているように思っていて、自分を担ってくれるものなど考えることもしない。
しかし、ひとたび病気になり、苦しみにあえぐことになったり、家庭の問題が深刻な状況になったり、職場にて耐えられないようなことが生じたときには、生きていけないと感じることが生じる。
そうでなくとも、若きときから、すでにこの世の問題や人間関係に悩み、この世の闇を思い知らされたときには、やはり生きることに望みがなくなる。
そのようなとき、このみ言葉にあるように、日々私たちを担って下さる神、その苦境から救って下さる神がおられるということを知ることはいかに大きな恵みとなることだろう。
自分で自分の苦しみや病気を担えない―老齢になるとこれはいっそう切実になる。 自分の犯した罪ゆえに事態がもとに戻らないことを深く思うほど、その自らの罪をも負いきれないと感じることになる。
また、家族に難しい病気をもった人、あるいは障がいをもった家族や、介護の困難な高齢者を担う責任のある場合、そのときも、担いきれない重さに苦しまねばならなくなる。
「星の王子さま」という童話に、ある星に酒飲みがいた。王子さまが、なぜ酒を飲むのかと尋ねたら、彼は、「忘れたいからだ」 と答えたというところがある。
これは、自分自身や周囲の人たちの罪深い現実に日々直面して、それをひとときの間でも忘れて、アルコールという化学物質の力で一時的に陽気になり、重荷などなかったような気持ちになりたいということである。
どんな人でも担えない重荷、それは死の力が迫ってくることだと言えよう。さまざまの内容をもった各人の日々の重荷の苦しみも、それは、その重荷が死に近づかせようとする力をもっているからである。
この詩の作者は、日々の重荷を担って下さる神は、人間の最終的な重荷である死ということからも解放して下さるということを知っていた。
主イエスは、「疲れた者、重荷を負う者は、だれでも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。」
(マタイ11の28)
と言われたが、この言葉は、上にあげた聖句と響きあうものである。
たしかに、キリストは死の力に勝利され、私たちに復活の力を与え、最終的に死の力からも解き放たれることを約束してくださっている。
この真理を信じることができるのは何と大きな恵みであるだろう。
私たちは、それぞれにこの地上の生活において、何らかの苦しみに出会うのは、必然的なことである。
それは病気、また孤独、あるいは事故、罪のゆえのあやまち、また災害…等々、人によってその苦難はそれぞれにことなり、当事者でなければ到底その本当の苦しさや悲しみはわからないであろう。
そうしたさまざまの苦しみは、何らかの神からの深い意味、メッセージが込められているというのが、いまから数千年昔の信仰の人の思いであった。
…主よ、あなたの裁きが正しいことを
わたしは知っています。
わたしを苦しめられたのは
あなたの真実のゆえです。 (詩編119:75)
私たちに日常生活のなかで、さまざまの苦しみや悩みが生じる。それは身近な家族、職場、あるいは友人との問題や自分自身の罪、あるいは他者の罪による苦しみがある。さらに他人には分かってはもらえない病気の痛みや苦しみがある。
それらすべては一体目的があるのか、実際に私たちがさまざまの困難に直面したときには、そうした事態が生じたことの目的など、なかなか考える余裕がない。
なぜ自分はこんな苦しい目に遭わねばならないのか、そのことを考えても分からないことが多い。しかし、なぜなのかという意味を、すべてをご支配されている神に向かって繰り返し求めていくとき、そしてそのような苦しい出来事からいくらか時間を経て、心を静めて祈るとき、神は愛の神であるゆえに、悪いことをすることはあり得ない、人間のように悪意をもって苦しめるということは決してない。この苦しみもはっきりとした目的がある、というように導かれていく。 この詩の作者は、自分の苦しみは神の真実のゆえだった、という驚くべき実感を記している。
ふつうはこの逆であり、自分だけこんなに苦しみに投げ込まれるのは、運命が自分を迫害しているのだ、あるいは○○という人間が悪いからこんなことになるのだ、といったように何らかの悪意が自分を苦しめている、というように受け取ってしまう。
私たちを苦しみに陥れる偶然的な事故や災害、あるいは人間の悪意など闇の働きのかなたに、神の愛と真実が見えてくるような世界、それこそ私たちが求めていることである。
地上のいかなる汚れや悪意にもよらずにその輝きを放ち続けている夜空の星の澄んだ輝きは、そのような世界が私たちの身近なところにある、ということを語りかけている。
この世での生活と、復活させていただいた後の天における完全な生について、イギリスの広く知られた詩人(*)が次のように歌っている。
(*)ロバート・ブラウニング 1812~1889年、イギリスのその時代の代表的詩人。
地にては壊れた弧。
天上では、完全な円となる。
On earth the broken arcs;
in heaven a perfect round.
この地上では、完全なものは何もない。一時的に造られても何かの打撃を受けるととたんに砕け散ってしまう。
いかに神のことを信じ、よきものを目指すためにこの世のものを捨てたような人であっても、特別な出来事が生じると、狼狽してたちまち逃げてしまう。そしてかつてはおもってもみなかったような、嘘を言ったりしてしまう。
見かけは完全な円に見えることがときとしてあろうとも、それは仮初めの円であり、影のようなものである。
キリストの弟子たちはまさにそのような状態だった。
キリストから、3年間も一日中ともにいて生活も同じくし、主イエスの他に類のない神の言葉をきいてきた。その以前にはきいたこともない奇跡の数々も直接に知らされた。それにかかわらず、弟子たちは、イエスが無惨にも逮捕され、連行されていくときには、たちまち逃げ去って、すぐあとで、一介の女性から、あんたもあのイエスという者の仲間だった、と言われるとたちまち、イエスなど全く知らない、と強い調子で否定し、さらに別の者にも言われてそれも否定し、三度までもそのようなことがあった。
イエスのひと言で、家族や職業までも捨て、そして毎日イエスに従ってそのだれも語らなかったような権威とわかりやすい言葉に無限の叡智のこめられた教えもつねにきいてきた。
それゆえに、彼ら弟子たちは、周囲の人からみたら、あるいは弟子たち自身も 完全な円のように 整って見えたことであろう。
それは、イエスが自分がまもなく捕らわれて十字架で処刑されると言ったら、ペテロはイエスをこともあろうに、自分のほうに引き寄せて、そんなことがあってはならない、と叱ったというほど、自分は偉いのだという慢心がふくらんでいたのだった。
そうした見せかけの円にたとえられる忠実な弟子の姿がこなごなとなり、一介の虚偽をいう罪人だと思い知らされた。
そんなことは、この世でだれの身にも常に生じている。
また、生きているときからその人生は悪の力にはまりこみ、悪事を重ねてさらしものになって激しい苦痛のなかで死んでいくという人もいる。十字架のキリストのとなりで処刑された重罪人がそれである。
かれのそれまでの人生は、不完全な弧どころか、幼児のときの愛らしい円状の存在が、さまざまの悪の誘惑にあって敗北し、幼な子のときのようなものが粉々にされ、悪の手下のようになったゆえに、彼の十字架処刑となったであろう。
しかし、そのような ずたずたに砕かれたような存在をも、ただイエスを救い主と信じて、仰ぎ見るだけで、地上にあるあいだから、すでにその粉々となったものが円のように新たに生まれかわり、その日のうちに完全な円となることが あなたは今日、パラダイスにいるのだ というイエスの言葉からうかがえる。
地上でいかに悪の力に砕かれて生きていけないほどとなっても、なお、そこから主を仰ぎ見るものは、ただそれだけで、イエスよりはるか数百年も昔の預言者が言っている。
…地の果なるすべての人たちよ、私を仰ぎのぞめ、そうすれば救われる。(イザヤ書45の22)
この詩の全文の訳とともに、原詩を次に引用する。
決して失われる善はない!
かつて存在したものは、以前のまま生き続ける。
悪は無に等しく、無価値である。また沈黙(静けさ)である。 だがそこからある響きが暗示されている。(*)
善きものであったものは善きものであり続け、
悪のためにこそ、さらに多くの善が輝く。
地上では不完全な弧があるが、天上では完全な円がある。
There shall never be one lost good!
What was, shall live as before;
The evil is null, is nought, is silence implying sound;(*)
What was good shall be good, with, for evil, so much good more;
On earth the broken arcs; in heaven a perfect round
(*)The evil is silence implying sound;というのはわかりにくいが、「悪は無であり、それゆえ何もうみださない静けさ(沈黙)でもある。にもかかわらず、それはある響きを暗示している。その本質は無である悪はその存在によって、善そのものをいっそう際立たせている霊的な響きがにじみでている。」といった意味。)
この詩には、善そのものー神は決して失われることなくいかなることがあろうとも、生きて存在しつづけるのだ、という確信が流れている。
神をなきものにしようとする悪の力は、強力に見えるが、実は無である。そしてそのような無である悪の力がこの地上にはびこっているが、そこからでさえ、かえって善そのものの永遠性を浮かび上がらせるというある種の響き(sound)をかもしだしている。
善そのものがいかに攻撃を受けて 一時的にはまたある地域その他で部分的に滅ぼされたようにみえても、それは一時的なもので、善そのものはずっと善きものでありつづける。
悪がはびころうとも、その背後でいっそう悪に勝利する力が浮かび上がってくる。
そうした状況は、地上ではばらばらの砕かれた円弧であっても、天においては、完全な円なのである。
この詩に記されている状況は、イエスの十字架においても見ることができる。
イエスは地上にあって究極的な愛と真実、そして正義を貫いて短いその伝道に命を注いだ三年間の生涯を歩まれた。
しかし、生前は、その伝道の最初から、真理を語ったとき、はじめはイエスの力あることばに驚嘆していた人たちも、数百年も前からの自分たちの罪を指摘されて、怒りだし、イエスを崖から突き落とそうとまでした。
しかし、イエスは、彼らのそうした激しい敵意のただなかを通って去って行かれた。(ルカ4の24~30)
そしてその後も、律法学者やファリサイ派の人たちから激しく憎まれるようになってついに 神を汚したという汚名をかぶされ、死刑を要求するほどにまでなって、ローマ総督でさえ、イエスには罪はないと言っていたのに、同じユダヤ人である彼らからの敵意によって十字架に釘付けという極刑となった。
そして、その全身を貫く激痛のさなかで、「わが神、わが神、なぜ私を捨てたのか!」との激しい叫びをあげて息絶えていくという壮絶な死となった。
これは、その生涯はなめらかな円どころでなく、ずたずたに寸断されたようなものだった。
しかし、そのような恐るべき悪意の勝利とみえた十字架が、全人類の罪というはてのない重い課題の完全な解決のための神のわざとなった。
天においては、罪の赦しという歴史上で何人もまったく不可能であったことを成し遂げられたという意味で、完全な円を描くものとなった。
さらにその三日後の復活ということで、これも全人類がうち勝てない死という力にうち勝つ道を、神の力によって復活し、人間の究極的な課題である死に勝利する道を世界に指し示したのだった。
このことも、またいかなる人間のわざも一歩も及ばない不可能な事を可能にしたということで、完全な円となった。
ユダが前もって計画的にイエスを金で売り渡したという大罪の罰はユダが受けたが、そうした悪事は、この世には現代までもいくらでも生じてきた。
しかし、そうした悪によってもすべてを見抜く力を神から与えられ、また武力を神の力で用いるなどもいっさいせず、みずからをユダが手先となって導いた武力装備した一団に捕らわれていった。
こうしたイエスの最後にまつわる悪の力も、それはイエスの神性を深く浮かび上がらせるということにつながった。闇の力はそれ自体無であり、神の前には無力であるが、そこから神の愛やその力がいかに大いなるものであるかということが、その闇の力のなかから浮かび上がってきたのだった。
使徒パウロは、こうした地上での切れ切れの弧は、天では完全な円となるーそれを次のような言葉で示した。
…神を愛する者たちーすなわち御計画にしたがって神から呼び出された人たちには、万事が共にはたらいて益となることを私たちは知っている。(ローマ8の28)
地上ではどうしてこんなことが起こるのか、なぜ自分にほかの人にはないような苦しいことがふりかかってくるのか…等々、いろいろな出来事が自分の現在や未来を砕くようにみえても、主のご意志によって選ばれ、この世から呼びだされた人においては、そうしたばらばらに見えるものがすべていわば完全な円となってつながるのだということになる。
そして、聖書の詩編が、じつにさまざまの苦難、裏切りや迫害、病気、また戦争などのこの世の修羅場のなかからの叫び、祈りが多く含まれているが、最終的に詩編の終わりのいくつかの詩においては、ハレルヤ!の大合唱が響いてくるような内容で締めくくられている。
…天において、主を賛美せよ
日よ、月よ、輝く星よ、
火よ、雹よ、雪よ、霧よ、
御言葉を成し遂げる嵐よ
野の動物たちよ、
翼ある鳥たちよ、
主の御名を賛美せよ
山々よ、すべての丘よ、
地上の王たちよ、
若者よ、老人よ、幼な子たちよ
主の御名を賛美せよ
威光(威厳)は天地に満ちている。
主に新しい歌を歌え
主は苦しむ人々を救いによって輝かせる。
主の力のあふれる大空において
その力強い御業のゆえに、
その大いなる力のゆえに
神を讃美せよ!(詩編148~150より)
これも、地上の数々の闇、苦難や悲しみもあろうともーすべてが細切れとされた弧であっても
天の世界を知らされた者は、それらすべてが神の力によって完全な円となっているのを実感する。
それゆえに、天地万物とともに賛美せずにいられないあふれる心を表しつつ、壮大な内容の詩編が閉じられている。
私たちの毎日の現実、世界の現実は、到る所で壊れ、心身の痛む傷があふれている状況である。
しかし、そうした破片ちらばる弧のようなものが、主の時いたれば、それらが美しい完全な円となっていく。
この世にあっても、聖なる泉の水を飲むことによって、そのような粉々になった私たちの心も主の愛によって欠けるところなき円となしてくださる。
戦後80年を経て、軍備は世界的に増強されていく傾向にあり、ドローンやロボットなどをもちいた新兵器も発達し、夥しい核兵器も保有され…。
憲法9条の精神はどこに行ったのかと思われるほどに、日本は公然と巨額の防衛費と称する軍事費増強がなされつつある。また、あれほどの被害があり、この巨大地震や大津波の危険性の高い日本での原発の立て替え、また新設などのことも公然と言われるようになった。
いつの時代においても、一部の政治家や軍事にかかわる人たちの考えが重要視されて、一般の民衆の意見や気持ちは無視されていく。
そのような目に見える世界の状況だけを見ているなら、知れば知るほどにこの世に絶望してしまうであろう。
けれども、はるか数千年前からこうしたこの世の状況と全くことなる世界をみつめて歩む人たちが生み出されてきた。
それは、このような人間世界という平面をみるのでなく、そこに立ちつつも、目に見えない世界からのおとずれを聞き取る人たちが生み出されてきた。
そのような人の一人が神から受けた啓示をしるしているが、次はその一つである。
…わたしの戒めに耳を傾けさえするなら
あなたの平和は川のように
正義は海の波のようになる。(イザヤ書四八の18)
平和を川のように、と感じる人は少ないのではないか。
また正義を海の波のようだ、といった表現も大多数の人にとってみたこともない表現であろう。
平和とは、何も戦争のようなことが起こらない静かな状態をいうと思われている。
しかし、戦後80年、憲法9条のおかげで、他国の戦争に加わらないで、日頃からの経済援助や、医療やその他の技術提供、文化的交流等々によって平和がたもたれるようにとの活動がなされてきた。
しかし、この憲法9条のもとであっても、人間の心は戦争のもととなっている自分中心の考え、金や権力の力で弱い立場の人たちを利用する、差別する、また利害が衝突して憎しみが生じ、事件となったり、またいじめやネットを用いた犯罪、またG7のなかでも自殺者の多いこと…等々、決して心のなかまで平和、平安であったということにはつながらないことも多い。
武力による戦争がなくとも、目に見えない心が相手を憎み、恨むことで戦いの状態となっていることも多い。
そうした人間の精神的な方面での戦いは、いかに平和的に見える世の中であっても存在しつづけていく。
聖書はそうしたすべての出発点である、一人一人の魂のなかにおける平和・平安をいかにして人々が受けとるのがということが中心的な課題となってきた。
そしてその問題は、すでに旧約聖書からみられる。
イザヤ書のこの箇所にある内容は、単に何事も波だったことのない静かな心の状況を指しているのではない。そのような静かな心というものは何か突発的な出来事があったらたちまち壊されてしまう。
それに対して、旧約聖書のこの個所では、平和というのは、たえず流れ続けるものであり、正義も絶えず打ち寄せる波のごときものとして言われている。
そして、このような動的なもの、あふれ出るという特質は、聖書の最初から言われている。それはエデンの園の四つの川ということで示されている。
ヘブル語では、平和、平安とは シャーローム という。この動詞形は、シャーラム、またシャーレームという言葉であるが、これは、神殿が「完成した」という個所にも用いられていることからわかるように、もともとは、「完成する」という意味なのである。
平和、平安という言葉(漢字)は、本来中国語であったのを日本に取り入れて使っている。
この言葉からして、平らで、和は、のぎ偏で 穀物を意味しそれを口で食べ合うことでの人々との交わりとか、平らで安らか というのであって、ヘブル語のように 完成するといったニュアンスはない。
シャーロームというのは、そうした言葉のもとから考えると、平和とか平安といった中国からの由来の意味とはことなり、完成された状態、を意味している。
私たちが、神を信じ、神の力で支えられているときには、私たちの波立つ心とか人々からの悪意などで混乱する心の状況が静まり、おのずからそうした外部からの誹謗、攻撃などをうけても、動じないということになる。
私たちの心が神の力や真実、愛で満たされるなら、おのずからそこから周囲に向って流れだしていく。
正義とされるということは、私たちと縁遠いものと感じられがちだが、キリストの十字架による私たちの不正(罪)の赦しを信じるだけで、神の前で正しいのだとみなされるようになった。
それは、新約聖書の福音の中心となっている重要なことであり、そのような信仰によって私たちは神から正しいとしてくださる。そうなると、私たちはつねに罪をおかす弱きものであるにもかかわらず、そのたびに十字架を仰ぐことで、罪赦されて日々新たな力を与えられる。
その赦しを海の波のように日々受け続けていくーそれは義とされたものへの赦しの言葉の連続のようなものになる。
私たちの生活は、健康であっても、勉強やスポーツなどで他者との競争、戦いのようなものに巻き込まれがちであるし、病気になるとあせりと不安、また友だちも来てくれない等々で、心は縮まってしまう人も多い。
そうしたことから、私たちにとって平和や正義が流れるように、また次々と打ち寄せる波のようだとは到底感じられない人々が多いと思われる。
それでも、このイザヤ書の言葉は、神からの平和や信仰によって神から正しいとしていただいた心にとっては、その罪の赦しを与えられる喜びゆえに平安が川の流れのように 心で実感するし、他方、正義などおよそ縁遠いような罪深きものであっても、十字架の赦しをつねに受け続けることで、それも赦しという神の愛そのものが打ち寄せる波のようになるという実感を与えてくれる。
この世界の平和は、こうした一人一人の魂の奥深いところでの出来事がもとにある。そこから人々の集りにもそのような平和が流れ始めていく。
心に残っている御言葉
「よくなりたいのか」 加藤久仁子(徳島)
皆さん、おはようございます。加藤です。今日の私の心に残った御言葉は、ヨハネ5章の6節「イエスは、その人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って、「良くなりたいか」と言われた。」
イエス様が病気でずっと動けない男の人に言われたその言葉、「良くなりたいのか?」それは私は前からちょっと不思議な言葉でした。当たり前に私たちは病気やら、いろいろな試練を早く無くしたいと思っています。それなのにイエス様は良くなりたいのか?とわざわざ聞いてくださる。
それは置いといて、最近私はとっても物忘れして、自分の忘れたら困ることは左手の甲に書くんですね。そうしたら忘れるのが少ない。でも、神様はイザヤ書49章16節のところで、「見よ、わたしはあなたを わたしの手のひらに刻みつける。」と言って下さっている。神様は何でもできるはずなのに、忘れないように、私たちのこと、愛するために、手のひらに刻むんですよね。
さて、さっき言った、イエス様が病気の男に聞いた、良くなりたいかというその言葉は今も私に聞かれているというのを思いました。たとえば、朝、はじめに聖書を読んで祈ると吉村さんが言うけれども、やっぱり忘れることがある。忘れないように、本当に私の本心、本当の気持ち。神様に従っていく。神様の弟子となる。本当にそれを確かめて、気持ち、覚悟があるかと、神様は聞いてくださっていると思いました。以上です。
(25.2.23 の主日礼拝にて)
心に残っている御言葉
あなた方のために立てた計画を…
林晴美(徳島)
心に残っている御言葉は、エレミヤ書 29章11、13~14節です。「わたしは、あなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、と主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。…わたしを尋ね求めるならば見いだし、心を尽くしてわたしを求めるなら、わたしに出会う、と主は言われる。」
生まれつき足の浮腫があり、原因も分からないまま子供時代が過ぎ、20歳のときに蛋白漏出性胃腸症の診断がつきました。けれども28歳ではじめて左側の胸水が貯まり入院するまでは正社員で働くことも出来ていて、そんなにむつかしい病気とはとらえていませんでした。33歳の時には胸水の量が増え入院、咳喘息も発症し、左腕の浮腫も出現しました。3年前には右側の胸水が増え、ステロイド治療は今も続いています。
症例が少なく、私の症状が増悪するたびに主治医の先生方も毎回模索しながらの治療となり、くわしい説明を聞くうちに私も病気に向き合う姿勢ができてきたように思います。
28歳の退院後は15年間の結婚生活、父が亡き後9年間の母との同居を経て、ひとり暮らし5年目です。
4回の入院やその後の生活環境、身体の状態は変わりましたが、すべては神様の立てた御計画の中にあり、35歳で集会に私を導かれ、主を求め続ける者とされるためであったと思わされています。診断されてから35年、信仰を持つ前の15年と持った後の20年、この違いは大きいと思います。
(25.3.2 の主日礼拝にて)
〇イースター特別集会
4月20日午前10時~13時
いつもの主日礼拝は、10時半からですが、イースターのときは、10時からです。
内容は、イースターメッセージ、参加者による感話(日々の主の恵みへの感謝。証し、心に残る御言葉、讃美歌などの歌詞、読書からのことなど)、賛美タイム等。
〇スカイプからマイクロソフト チームズへの移行について
私たちの徳島聖書キリスト集会で、大学病院に長期入院の寝たきり、人工呼吸器装着で、首から下がいっさい動かせない勝浦良明さんが礼拝集会にオンライン参加できるようにとの目的で、スカイプを併用するようになったのが、2010年3月でした。それによって勝浦さんも病室から毎週礼拝に参加できるという道が開かれ、それから15年間、スカイプを使ってのオンライン参加ができ、今日に至るまで多くの県内外の方々が参加できてきました。
しかし、今年の5月からは、
「グーグル ミート」(Google Meet)というものに移行します。数人の徳島聖書キリスト集会の方々によってその移行のための対応をしてくださっているところです。
そのことに関しての問い合わせは、末尾の吉村孝雄または、次の方々に直接にメールで、またその方々の電話は番号は吉村に問い合わせあったときにお知らせします。
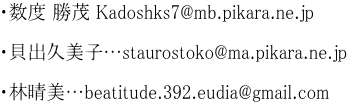
・主題…「福音の希望ーコロサイの信徒への手紙に学ぶ」
日時 2025年5月10日(土)午後1時~11日(日)午後1時。
場所…関西セミナーハウス
〒606-8134 京都市左京区一乗寺竹ノ内町23
TEL:075-711-2115
交通:JR京都駅から
○地下鉄烏丸線 北山駅16分下 2番出口、 タクシー約10分
○市バス⑤系統に乗車、約50分。 「修学院道」下車 徒歩15分
会費:全日参加 一万七千円
一泊3食、11日の昼食代も含む
部分参加 二千円
日曜昼食 一一五〇円
申込先: 宮田咲子
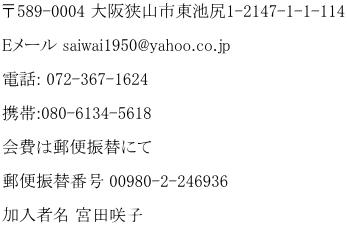
プログラム 予定
10日(土)
12:30~13:00 受付
13:00~14:10 開会礼拝
聖書講話 木村護郎クリストフ
14:20~15:00 賛美タイム
自己紹介・証(1)15:00?15:30
休憩・写真撮影 15:30~18:00
自己紹介・近況報告(2)
18:00~19:30 夕食・自由時間
19:30~20:40 夕拝
グループに分かれて
21:00~22:00 若者の会(希望者)
11日(日)6:30~7:30
早朝祈祷会 散歩
7:30~8:50 朝食、自由時間
8:50~11:00 主日礼拝
聖書講話 (1) 小舘美彦
聖書講話 (2) 吉村孝雄
11:20~12:20 閉会の集い
参加者の感想・分かち合い
12:20?13:20 昼食
〇多くの方々からのお祈り、来信、そしてその祈りの込められた協力費を感謝です。
去年の晩秋のころから妻の恵美子さんの病状が全面介助の状態となって、そのため妻は、急な山坂を登る小松島市の山の家には帰れなくなり、徳島市、そして板野郡北島町など三カ所を往復などせねばならなくなり、時間もさらに多くとられていろいろな返信などもできないままになることが多く申し訳なく思っています。
〇集会案内
主日礼拝 毎週日曜日 午前10時30分から。徳島市南田宮1丁目の集会所とオンライン併用。
以下は、天宝堂集会と、第四火曜日の北島集会は対面とオンライン併用。海陽集会はオンライン(スカイプによる)集会。参加希望の方は、左記奥付の吉村まで連絡ください。
〇 夕拝…毎月第一、第三火曜日夜7時30分~9時
〇 家庭集会
① 天宝堂集会…毎月第二金曜日 午後8時~9時30分
② 北島集会…・戸川宅にて(対面とオンライン併用) 第四火曜日13時~14時半
・第二月曜日 午後1時~
③ 海陽集会…毎月第二火曜日 午前10時~12時
)
---------------------------------
主筆・発行人 吉村孝雄(徳島聖書キリスト集会代表)〒七七〇-〇〇〇四 徳島市南田宮一丁目1の47 電話 080-6284-3712 固定 0885-32-3017(FAX共)E-mail: emuna@ace.ocn.ne.jp 〇この冊子は、読者の方々からの自由協力費で作成、発行しています。協力費をお送りくださる場合には、次の郵便振替口座を用いるか、千円以下の場合には切手でも結構です。
郵便振替
口座番号
01630-5-55904 加入者名 徳島聖書キリスト集会
〇http://pistis.jp
(「徳島聖書キリスト集会」で検索)