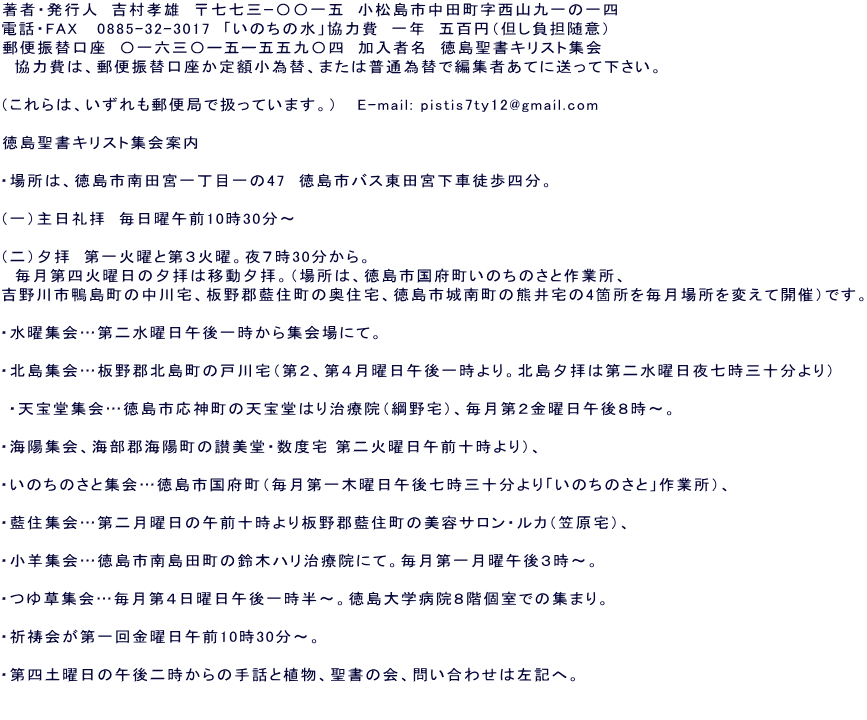二 〇 一 六 年 四 月 号 六 六 一 号
|
主よ、それなら何に望みをかけたらよいのでしょう。 私はあなたを待ち望みます。 (詩篇39の8より) |
・2016年4月 第662号 内容・もくじ
神は私たちに対して常に、「生きよ!」と強く呼びかけておられる。
聖書とは、そのことを中心として次々と内容が増加していった書物である。
しかし、この世においては、すでに子供のときから、クラスの生徒などに対して「死ね!」と言ったりするほど、気に入らない他者が死ぬことを願うような闇の心が巣くっているのである。
先ごろの国会で、保育園に子供が入れなかったとのことで、若い女性が、「保育園落ちた日本死ね!!! オリンピックなどに何百億円も使って、保育園などにどうして費用をかけないのか。…」とインターネットのブログに書いたことから大きな話題となった。
子供が保育園に入れない―そうなると母親も仕事をも辞めねばならなくなる、これは当事者にとっては重大問題である。その苦しい状況ゆえに、このように書いたのであろう。
しかし、「日本死ね!!!」 という表現が安易に用いられるということは、友だちに「お前、死ね!」と軽々しく言ったりするような状況のなかで育った人なのだろう。
人間は、気に入らない人間を、目の前から排除したくなる。その極端な表現が、〇〇死ね!ということである。こうした本性が、さまざまの人間関係を傷つけ、破壊し、大きな問題ともなりかねない。
東日本大震災から5年、いまだ17万人を越える人たちが仮設住宅にて不安定な生活を続けている。
原発の近くの領域においては、今後とも荒廃は続く。先ごろの報道では、広大な住宅地、市街地が、野生動物の横行する領域となっていて、本来は山でしか行動しない猪が大量に、そうした荒廃した住宅地、市街地に繁殖し、住み着いている状況が放映されていた。
原発はこのように、莫大な被害を与え、費用も人間関係も郷里も絆も断ち切っていく。 原発の大事故があると、さまざまの人間の生活領域に死をもたらしていく。
原発の高い放射能を持つ廃棄物があるかぎり、そこは再生できない。また、再処理をした後にできるガラス固化体に近づくと20秒で死に至るという強力な放射線が出されているという。
このように、近代科学の粋を集めた産物が、人間関係を破壊するものとして存在しつづけていく。
およそ、さまざまの武力は、それが用いられたら多くの人たちが殺傷される。それゆえに、武力を用いようとすることは、多くの場合、相手に対して、「死ね」ということである。数千万という人々を殺害することになった、二度の世界大戦は、おびただしい人に対して「死ね」ということを実行していった。
これに対して、聖書の世界では、破壊され、死に至るほどの状況から復活、再生されるといことが一貫して主題となっている。
このことについて、旧約聖書の重要人物に関する記述を見てみよう。 まず、創世記に現れて、詳しくその生涯が記されているヨセフは、兄弟たちから殺される寸前にあったが、辛くも主から逃れて後に王の側近となり、神の英知が与えられ、未来のことを啓示によって知らされ、それによって民を飢饉から救った。
モーセも、エジプトの王女に育てられ、王子としての身分であったが、ユダヤ人であることが発覚し、命をねらわれ、死を覚悟してはるかに遠い地方へと逃げ延びた。 かれは、一度は死んだも同然となっていた。しかし、奇跡的に生き延びて、その地の女性と結婚し、羊飼いとして平和な生活をしていたが、そこから神の呼び出しがあり、エジプトにいる同胞を奴隷状態から救いだすという大いなる使命を受けた。
モーセも死んだも同然の状態から、神によって生かされ、やはり滅びへと向っていた多くの同胞をも生かすことにつながった。
そしていまから三千年ほども昔のダビデ王も仕えた王から妬みのために長期間にわたって追われ、殺される寸前といった状況にも立ち至った。また、後にそうした苦難を通して王になったが、その後、息子から王位を追われ、殺されそうになった。このような死の陰の谷をさまよったが、そこからも生かされて、命のあふれる詩を多く作り、それが讃美歌の源流となって世界に伝わっていった。
このように、旧約聖書でとくに重要な人物は、死んだような状況から、神への信仰により、そこから与えられた神の力によってその死の深い闇に落ち込もうとしていたところから救いだされ、新たな命を与えられた。
聖書はこうしたとくに重要な人物を用いて、神のご意志が再生、復活にあるということを示しておられる。
それゆえに、詩篇の第一篇が詩篇全体の巻頭言であるように、創世記の最初の記述は、聖書全体の巻頭言となっている。聖書とはまさに闇、死のなかに光を与え、命を与える書である。そしてこれが神の御心なのである。
主イエスも、天の国は誰のものか―それは霊(心)において貧しきものと言われた。すなわち、魂の深い部分において自分は何も良きものをもっていない、という実感である。よいものがあるとしてもそのよいものは持続しない、絶えず他者からの賛辞とか報いがなかったら続かないものであると知っている心である。
言い換えれば、それは罪を知る心である。さまざまの意味における弱さを知る心である。
天の国とは神の国であり、神の御支配そのものであり、その御支配の内にあるものである。神の御支配とは、人間の支配のように権力や金の力、また暴力、軍事、経済力による支配等々でない。純粋な愛と正義の支配であり、それは全能の神の御支配であるゆえに、死というこの世でいっさいを呑み込んでしまう力をも支配する力である。
闇とは死の世界であり、死に近くなることもまた闇である。重い病気、脳や内臓の損傷などの重傷、人間関係が極度に悪化して互いに憎しみを持った状態―等々は、みな闇である。
その闇の力に呑み込まれない力があること、それを光―命に変える力が存在することを聖書の最初から述べている。
命と光―それは、科学的に見ても深い関わりがある。太陽の光がなかったら、ほとんど一切の生物は生きていくことはできない。私たちの食物も、野菜や果物などは、直接的に太陽の光のエネルギーによって作られているし、魚や肉などは、その餌となるものが太陽の光のエネルギーによって生み出されているから結局そうした魚や動物の肉も太陽エネルギーによる。 太陽の光は、まさに命の光である。
このような命と光の関係は、霊的な世界においてさらに深い。主イエスは次のように言われて、この二つの関係がキリストによって深く結びつけられていることを示された。
…「わたしは世の光である。わたしに従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。(*) (ヨハネ8の12)
キリストの命とは力、それは死からよみがえらせる力である。最大の力である。
(*)「命の光」という重要な言葉は、外国語の表現では次のようになる。
the light of life(英語では、ライト、ライフ というように、発音も似ている。)、das Licht des Lebens(ドイツ語 ダス・リヒト・デス・レーベンス) la lumiere de la vie (ラ・ルミエール・ドゥ・ラ・ヴィー フランス語)
このように、神の光は同時に命をもっているゆえに、パウロはキリスト教徒を迫害しているさなかに、天からの光を受け、新たな命によみがえった。
パウロはキリスト教の真理に真っ向から反対し、キリスト信徒を滅ぼそうとまでしていたにもかかわらず、命の光が注がれると、突然変えられた。このことはとくに劇的なことでパウロだけがそのようになったと思われがちだが、そうでなく、その程度の多少はあれ、キリスト者となった者はみな、キリストの真理に背いていたところに上よりの命の光を受けて変えられたのである。
パウロはみずからの経験からも、また聖霊によって示されたことからも、すべての人は、神の完全に照らしてみるときには、死んだ状態だということを語っている。
…さて、あなたがたは、以前は自分の過ちと罪のために死んでいた。
しかし、憐れみ豊かな神は、わたしたちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、キリスト・イエスにあって、共によみがえらせ、共に天上で座につかせて下さったのである。 (エペソ書2の1~6より)
このように、死の力にとらわれていたものを、神の力を注ぐことによって生き返らせてくださった。復活ということは、肉体の死後のことだけでなく、生きているうちから、新たな命をくださって新しい歩みをはじめることにも用いられている。
他方、科学的に見ても、確実に私たちの地上の命は死に向っているのであって、一人一人に、「お前はまもなく死ぬのだ、時が来たら死ね!」 といわれているようなものである。
それに対して、聖書の世界は―言い換えると神の御心は、「生きよ!」という、あつい思いなのである。
…わたしはだれの死をも喜ばない。
お前たちは立ち帰って、生きよ、」と主なる神は言われる。(エゼキエル書18の32)
主イエスが、聖書のなかで唯一、大声で言ったと記されているのは、次の箇所である。
…祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、
イエスは立ち上がって大声で言われた。
「渇いている人はだれでも、わたしのところに来て飲みなさい。
わたしを信じるものは、聖書に書いてあるとおり、
その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。(ヨハネ7の37~38)
これは、それほどこのことが重要だからである。渇いている者―これは日本のような水が到る所で流れているところでは、よく分からない。砂漠地帯、イスラエルのような4月から10月まで半年余りも全く雨が降らないような乾燥地帯では、水がない、渇いた状態でそのままいれば死んでしまう。単に私たちが少し水を飲まなかったらのどが渇いたというようなものとは根本的に異なる。
生きるかどうかという問題なのである。
そのようななかで言われたことであるゆえに、この渇いているものは来れ、イエスが与える水―命の水を飲め、ということは、すなわち、「生きよ!」ということなのである。
このような、いのちの水を与える御方が存在することは、イエスより数百年も昔から、預言されていたのに驚かされる。
…「さあ、かわいている者はみな水に来たれ。
金のない者も来たれ。
来て買い求めて食べよ。
あなたがたは来て、金を出さずに、ただでぶどう酒と乳とを買い求めよ。
なぜ、あなたがたは、かてにもならぬもののために金を費し、飽きることもできぬもののために労するのか。わたしによく聞き従え。そうすれば、良い物を食べることができ、最も豊かな食物で、自分を楽しませることができる。(イザヤ書55の1~2)
もう死んでしまいたい、死んだらどれほど楽になるだろう…と深い悲しみや苦しみにある人たちは、数知れずいる。そうした方々がこのイエスの、そして神のお心にふれ、来れ! と呼びかけている御方のみ声に聞くことができるなら、どんなに大きな恵みだろう。
神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。
苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。
わたしたちは決して恐れない、
地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとも (3節)
海の水が騒ぎ、湧き返り、
その高ぶるさまに山々が震えるとも。 (4)
川とその流れは、神の都に喜びを与える、
いと高き神のいます聖所に。 (5)
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。
夜明けとともに、神は助けを与えられる。(6)
すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神が御声を出されると、地は溶け去る。 (7)
万軍の主はわたしたちと共にいます。
ヤコブの神はわたしたちの砦の塔。 (8)
主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を圧倒される。
地の果てまで、戦いを断ち、
弓を砕き矢を折り、盾を焼き払われる。(10)
「静まって私こそ神であることを知れ。わたしは神。国々にあがめられ、この地であがめられる。(11)(*)
万軍の主はわたしたちと共にいます。ヤコブの神はわたしたちの砦の塔。(12)
(*)新共同訳では「力を捨てよ」と訳されているが、原文には、「力」という語はなく、原語のラーファーは、単に「捨てる、やめる(詩篇37の8など)、リラックスさせる、弱る、失う」などと訳される言葉である。それゆえ、これは「まず自分の考え、他人の考え、世の中のできごと等々を思い浮かべたり思案するのでなく、それらを捨てて、神に向かえ」という意味。
それは、すぐ後に続く「私こそ神であることを知れ」につながる。口語訳は「静まって」。英訳などでは Be still 「静まって」と訳しているのが多数を占めている。
・ Be still, and know that I am God! (NRS,NIV他)
・Be still and acknowledge that I am God (NJB)
詩篇46編は非常によく知られた詩である。この詩の特徴はどんなことがあっても揺らがないという確信にある。私たちに必要なのはこの確信である。これは勉強や人生を重ねたから出来るものではない。
かえってさまざまのこの世の不正や混乱に巻き込まれて、永遠の真実とか正義などはないのだ、といった考えに染まってしまう人も多い。
学問や、科学技術の産物、そしてさまざまの海外や国内の旅行、多くの知識等々がなくても、この詩篇に記されているような確信を与えられ、この世のあらゆる問題に直面しても人を恐れず、神を畏れる人たちは常に起こされてきた。
しかし、現代の日本においては、この確信を人々に与えるものが欠けている。
それはこのような確信は、教育や科学技術や経済の発展、インターネットなどによるさまざまの知識等々によっては得られないからである。
知識によっても生まれつきや教育、あるいは訓練や、芸術やスポーツなどの才能、国内外などでの多様な経験―いかにそのようなものを重ねても得られないのが、こうしたこの世界全体の動きや、その最終的な状況に関する確信である。
それゆえ、この詩が作られたのはいつごろなのかはっきりとはしないが、少なくとも二五〇〇年ほども昔から、こうした確信は変ることなく受け継がれてきた。時間や政治、社会、習慣や民族のあらゆる違いを越えてこの確信は揺らぐことはなかった。
3~4節では最大級の混乱を表現している。海は聖書ではしばしばサタン的なものを象徴している。3000年も前は海はどれだけ広くどれだけ深いか分からなかった。コロンブスの時代になって、地球は平面ではなく、丸いものだということが初めて分かった。
ということで、海が一度荒れたら、どんなものでも飲み込んでいき、海の水が騒ぐというのは悪魔的な力が襲ってくる、困難に陥れることがあると考えられていた。
この悪の力によって山々が震えるとは私たちが考えないような表現である。分かりやすく言えば、この世の中が悪の力によって大混乱になって、普段は揺るがないはずの山々ですらも震えがあるような、非常に大きな出来事を言っている。しかしこんなに大混乱が起ころうとも、全能の神を信じ、その力に頼っているかぎり、恐れることはないのだということを言っている。
この世界は耐えずこのよう確信を覆すようなことが次々と起こってくる。家族や職場などの人間関係がいちじるしく悪くなったら動揺して生きていけない人もいる。また死が間近に迫った大きな病気や事故に出会った時にはまさに動かなかった心が、激しく動揺することもある。
しかしこの詩人はそのようなことがあっても、恐れないと言っている。これは神は不動の存在であるという確信があり、また固く神と結びついているからである。神はどんな時にも守ってくださるという確信は一体どこから来たのか。これは様々な人生経験からというのもあるが、根本的には神様からの啓示がなければ与えられない。苦難の時に必ず助けてくださる神がおられ、その神からの語りかけがあってはじめて大いなる苦難のときにも耐えていく力が与えられる。
3年間もイエスに従ってきた弟子でさえ、自分の師匠たる主が逮捕されるという思いがけない事態に直面して、たいへんな動揺が生じて皆逃げてしまった。その弟子たちでも復活の後、聖霊を注がれて確かにこのような確信を与えられていった。ステファノも殉教の時に動揺せず恐れなかった。
…一つの川がある。その流れは、神の都に喜びを与える。
高き神のいます聖なる住まいを喜ばせる。(5節)
この世は海のごときもの、それは荒れ狂う力を持ち、あらゆるものを呑み込むような闇の力をもっている。
それと対照的に、同じ水であっても、命を与える川の流れのことが記されている。(*)
(*)新共同訳は、「大河」と訳されているが、他の日本語訳では単に「川」と訳されている。原語のナーハールは、数十種ある英訳でも、ほとんどが stream(小川)または、単にriver(川)と訳されていることからうかがえるように、この原語は、小さい川も大きな川も意味する。
神の都とはエルサレムをさす。エルサレムは標高835メートルの山の上の町で、川もなく、大きな川が流れることはあり得ない。これは象徴的な意味で書かれている。
乾燥地帯のただなかにある高い山、そこには目に見える川は流れていないが、神の命の水の流れが存在するのを、この詩の作者は啓示されたのである。
このような啓示は、旧約聖書の重要な預言者の一つ、エゼキエル書にもみられる。
…水は神殿の敷居のわき上がって東へと流れていた。…
この川が流れていくところではどこでも生き物は生き返る。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。
(エゼキエル書47の1~12より)
このように、いかに乾燥したところであっても、目には見えない霊的な水―いのちを与える水の流れがあるという。
このことは、のちにキリストが、私を信じる者は、心のうちに命の泉が与えられ、そこからあふれでると言われたことを思い起こさせる。(ヨハネによる福音書7の37~)
前半に書かれているような神の助けに関する不動きの確信を持っている時には、豊かな祝福、いのちの水の流れが与えられるのである。これはそのまま現代に生きる私たちへのメッセージとなっている。
創世記の2章には、エデンの園の記述があり、その川の流れが園を潤し、世界に流れていくというところがあるが、そこのイメージがこの箇所にある。いつも神様がその確信の中にいてくださる。他の国々は神と繋がっていないから揺らぐ。
…すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神が御声を出されると、地は溶け去る。(7節)
どんな強固なものであっても、神の一言があればいとも簡単に、溶けると言われるくらいに簡単に失わせることが出来る。神の力をこのような表現で言っている。
…万軍の主はわれらと共におられる、ヤコブの神はわれらの避け所である。 (8、12節) 8節と最後の12節では、同じことばが繰り返されている。 それはこの単純な神への信仰と信頼こそ、あらゆる困難にもうち勝つ力を与えてくれるものであることを深く啓示されていたことを示す。
そして、その確信をみんなで共有するために歌と曲が付けられて、重要な部分をみんなで折り返して讃美した。全体のことを2行に凝縮している。万軍の主とはすべてのものを従えている主という意味である。
…来たれ、見よ、主のみわざを!(*)
主は驚くべきことを地に行われた。(9節)
(*)新共同訳では、「主の成し遂げられることを仰ぎみよう」となっている。しかし原文には、ここにあげたようになっている。それゆえに、ほかの日本語訳―口語訳、新改訳などもも「来たれ見よ、主の御業を」となっている。英訳も、Come and see what the Lord has done.
主の業というのは確信を持っている人により啓示される。不動の確信を持っているということは、神としっかり結びついているので、一層主が成し遂げられることが分かる。確信を持っていなければ見えない。生活の中で遭遇するいろんなことも、神への確信を持っていたら、いろんなことが神がなさっていると感じることができる。
しかし神など存在しないと思う人にとっては、何が起こっても偶然である。
神がこの世の力を圧倒されるお方である。神に敵対する力を驚くべき仕方で滅ぼされる。
そして世の終わりのときにはどのような状況が生まれるのかが、預言的に記されている。
…主は地のはてまでも戦いをやめさせ、弓を折り、やりを断ち、戦車を火で焼かれる。 (9節)
最後の部分は、最終的にはあらゆる武力が断たれるという約束である。こうしたところにも聖書の非戦論の源流がある。
しかし、これは人間の努力とか運動でなされるといっているのでなく、終末において、神の全能の力により、神の御計画にしたがってなされるということなのである。
…静まって、わたしこそ神であることを知れ。
わたしは国々のうちであがめられ、全地にあがめられる。 (11節)
心を静めて神を仰ぐとき、その神は天地創造の全能のお方であり、苦難のときにもその力をもって助けてくださるお方であることが自然に実感されてくるが、静まることのない心は、世の中の力、自分の力のなさなどによって確信は失われ、不安と動揺が心を支配するようになる。そして本当にあがめるべきお方は神だということが分かる。
この詩の最後に、すでにふれたように、次に強調されている言葉がある。
…万軍の主はわれらと共におられる。ヤコブの神(*)はわれらの避け所である。
(8、12節)
(*)「ヤコブの神」といった表現は、現代の私たちにはなじまない。ヤコブと、はアブラハムの孫に当たる。イスラエル民族が信じた神ということであり、歴史を通じて受け継がれてきた神ということが示されているが、ヤコブなどといっても何のことか不明である大多数の日本人にとっては唯一の神と置き換えた方が分かりやすい。
この世のさまざまの闇の力や、混乱が我々にまつわりついてくる。しかし、信じる者には、全能の神がいかなる時にも共にいてくださる―この単純な真理が数千年を貫いて受け継がれてきたのである。
このようにこの詩は初めから終わりまで、個人の悩み、苦しみではなく、人間に与えられる究極的な確信がはっきりと示されている。
宗教改革者マルティン・ルターもこの詩を非常に愛好して、この詩によって宗教改革も支えられ、宗教改革を推進する音楽にもなったくらいである。讃美は単に楽しいから歌うというだけのものではなく、活動を支え、導いていくという力に満ちたな役目をも持っている。
現代の私たちにおいても山々が揺らぐと例えられるくらい大きなことがいつ起こるか、分からない。
科学技術が生み出した核、核兵器と、その副産物である原発―これらが、テロに用いられるときには、だれも想像できないような事態が生じることが予想される。
そんなときに何が一体私たちをとらえてくださるのか。ただ、天地創造の神、すべてを支配される全能の神以外にはない。
この詩は、はるか二千数百年も昔に作られたものでありながら、現代の大いなる混沌に向けても、その永遠の光を力強く投げかけているのである。
ああ、幸いだ
悲しむ者たち。
なぜなら、その人たちは、(神によって慰められ)力づけられるからである。(*)
(*)「慰められる」原語は、パラカレオー。これは、例えば「 見よ。あなたは多くの人を訓戒し、 弱った手を力づけた。(ヨブ記4の3)」のように、ヘブル語のハーザク(力づける)のギリシャ語訳として用いられている。
日本語の「慰める」は、泣いている子の頭をなでて泣かないで―というようなイメージがあるが、原語はそうしたあたたかいイメージとともに力を与えて立ち上がらせるといったニュアンスをも持っている。
私たちの世界には、生きていく過程においては、さまざまの悲しみがある。自分自身、また私たちのキリスト集会に集う人たち、さらに広くこの世には、この世に生きるかぎり、それぞれに悲しみがある。
トルストイの大作「アンナ・カレーニナ」の冒頭に、「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである。」という言葉がある。
この大長編の最初に何をもってくるか、著者もいろいろと考えたことであろう。
そして彼自身の経験と世界の状況をみるとき、この言葉が心に浮んできたのではないか。
確かに、幸福と思われる家庭は、家族が健康、夫婦円満、子供も成績もよくスポーツにもすぐれていて、人気がある―このような状況を幸福な家庭だとみなす。
しかし、不幸と言われるものは、実に、千差万別である。家族の不和―それは誰でも不幸と思う。しかし、その状況は、だれかの病気、事故、親子、夫婦の衝突、憎しみ―子供の病気、異常、成績、学校でのいじめ…等々。病気にしても、どこがどのような病気であるのかによっても苦しみは違ってくる。
日本や世界のニュースには、いつも悲しみにあふれる内容が満ちている。いろいろな犯罪、それを受けた人たち、また起こした人たち本人だけでなく、その家族もその状況によっては生涯深い悲しみ、嘆きの日々となる。
津波や原発のような災害によっても取り返しのつかない悲しみが生じる。家族、そして故郷、さらに仕事や人間関係の喪失、等々、二度ともとにもどすことができない状況に突然追い込まれた人たちの悲しみ。
また、世界の各地には、飢えや貧困、また戦乱による悲しみが渦巻いている。難民となって故郷から命の危険をおかし、行く手に何があるかも分からないまま、祖国から脱出していかねばならない、小さな子供、老人、病人、障がいもった人たちなど、どのような苦しみや悲しみがあるだろう。
もし、そのような人たちの声が聞こえるとすれは、おびただしい嘆きと悲しみの声が満ちていると思われる。
そうした、経済的、社会的な苦難に置かれていない日本やヨーロッパの多くの国々にあっても、そして家族も自分も健康で生活も安定していてもなお、老年のさまざまの悲しみが生じてくる。病気、家族の死別、離反、孤独、身近な家族の無理解―等々。
また、家族が病気や老年によって変質していくこと―かつての愛していた状況と全く異なる人間になっていくことを目の当たりにするときの深い悲しみもある。
さらに、災害や政治的、社会的な困難、年齢、地位などにかかわらず、どのような人間にも生じうる。
それは、私たちが正しい道を歩めない(罪)、ということからくる悲しみである。
過去に、自分の罪―あのようにしたからこんな事態が生じたのだ、ということが深刻な事態であるほど、もう取り返しがつかないことを知らされるだろう。
それは、その相手に犯した言動の罪の重さを知らされるときである。
こうした自分の外の世界にも、内なる世界からも悲しみはつぎつぎと生まれてくる。打ち寄せる波のように。
そのような状況に直面して私たちの心は、その悲しみに打ち倒されていくか、無感覚になるか、それともそこから新たな力を与えられて歩んでいくかに分かれる。
宮沢賢治はそうした深い悲しみの世界を体感していた詩人であった。
…すべてさびしさと悲傷とを焚いて(*)
ひとは透明な軌道をすすむ(宮沢賢治「春と修羅」)
かなしみはちからに、
欲りはいつくしみに、
いかりは智慧にみちびかるべし(「書簡」)
(*)悲傷(ひしょう)痛ましい出来事にあって、深く悲しむこと。
さびしさや悲しみとそこから受ける傷を焚いていく、それを燃料として歩むという。悲しみは深ければ深いほど人の魂を打ち倒してしまう。
使徒パウロは、滅びに至る悲しみについて語っている。
しかし、それを魂を破壊するものとしてでなく、前進するための燃料として与えられているのだと、受け取る。
それゆえに、「かなしみはちからに」導かれるのだ、という確信が生まれる。
こうしたすべてを、主イエスは、「ああ、幸いだ。悲しむ者は。なぜなら、その人たちは、神によってはげまされ、慰められ、力を与えられるからだ」と言われたのである。
失われた者を尋ね求め、傷ついたものを包む神 (旧約聖書・エゼキエル書34章より)
預言者エゼキエルは、主イエスより六百年ほど前の預言者で、紀元前五九四年に神のはっきりした啓示を受けたとされている。
彼は、エルサレムから一五〇〇kmほども離れたバビロンので捕囚となっていた。そこに神の啓示があった。
神の啓示というのは、どのような状況であっても与えられ、天が開けることがあるのだと知らされる。
アブラハム、モーセ、主イエスの弟子やステパノにもそのような啓示があった。
啓示、その内容は、どんな人間の創作にも及ばない。創作はあくまで創作であってそれが真理であるということとは直接には関わりがない。
しかし、聖書における啓示は真理そのものが直接に示されることである。
…災いだ。自分自身を養うイスラエルの牧者。牧者は群れを養うべき者ではないか。
ところが、あなたがたは乳を飲み、毛織物をまとい、肥えたものをほふるが、群れを養わない。
あなたがたは弱った者を強くせず、病んでいる者をいやさず、傷ついた者をつつまず、迷い出た者を引き返らせず、うせた者を尋ねず、彼らを手荒く、きびしく治めている。
(エゼキエル書34の2~4)
最初の「災いだ」は原語では「ホーイ」(間投詞)で、「あぁ、何ということだ。」というニュアンスがある。イスラエルの指導者たちは、自分自身を養っている。神の御心の逆を行い、却って踏みつけて、自分たちを肥やしている。今の政治も同じようなものである。しかし神は生きて働いている。
神が直接介入するとある。神ご自身が群れを救い出す。神のご性質は、弱いものを助け出す。羊飼いが、群れを探すように、ご自分の群れを探し、散らされたものを救い出す。全ての場所、不可能な場所からも連れ戻す。絶望的な者たちを集め、直接神が養う。
…主なる神はこう言われる、見よ、わたしは、わたしみずからわが羊を尋ねて、これを捜し出す。
牧者がその羊の散り去った時、その羊の群れを捜し出すように、わたしはわが羊を捜し出し、雲と暗やみの日に散った、すべての所からこれを救う。
わたしは彼らをもろもろの民の中から導き出し、もろもろの国から集めて、彼らの国に携え入れ、イスラエルの山の上、泉のほとり、また国のうちの人の住むすべての所でこれを養う。
わたしは良き牧場で彼らを養う。その牧場はイスラエルの高い山にあり、その所で彼らは良い羊のおりに伏し、イスラエルの山々の上で肥えた牧場で草を食う。
わたしはみずからわが羊を飼い、これを伏させると主なる神は言われる。
わたしは、失せたものを尋ね、迷い出たものを引き返し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くし、肥えたものと強いものとは、これを監督する。わたしは公平をもって彼らを養う。
(エゼキエル書1の11~16より)
ここで言われている「失われた者を探し出す」という側面は、その後でも繰り返されている。
それが神の御心で、探し出そう、救い出そうとする神の愛がはっきりと示されている。 この精神がのちに主イエスにそのままつながっていく。
傷ついたもの、弱いものを探し求めてくださるイエス・キリストの姿が預言されている。
詩篇119篇は「神の言葉」をメインテーマとして一貫して語り続けている。そしてその詩の最後の言葉はエゼキエル書の言葉と共通している。
「わたしが小羊のように失われ、迷う時、どうかあなたのしもべを探してください。
あなたの戒めをわたしは決して忘れません。」(詩篇119の176節)
旧約聖書は裁きの神、正義の神であり、新約聖書の神とは違うと言われたりすることがあるが、それは一面的な見方である。
たしかに旧約では、神の御計画の中で、まだ最終的な啓示は与えてはおられなかった。 例えば、割礼をしないと滅ぼされるとか、一夫多妻、あるいは血を食べるものは、滅ぼされる…等々。
しかし、神の啓示は、ご計画によって、歴史のなかで徐々に深く、広げられていく。
私たちは旧約聖書の表現の背後にあるものを聞きとらなければいけない。旧約聖書はキリストを指し示している。 キリストが言われた失われた羊の譬え(マタイ18の12~)は、ここであげた箇所でもわかるように、すでにエゼキエル書や詩篇で言われていたことであり、それはキリストを指し示すもの、預言であったのである。
また、良き羊飼いのたとえも主イエスが言われたことであったが、すでに神は主イエスの600年も前に、すでに引用したように、エゼキエル書において完全な善き羊飼いのことが指し示されていたのである。
「主イエスは失われ迷い出た私たちを助けてくださった。」キリスト者となった人はそういう実感を持つ。だからこそ、それを弱い人たちに伝えていきたいという願いが生まれる。
身体が不自由で十分動かない人、美しい音楽が聞こえない人、美しい絵が見えない人もいる。
しかしキリストの愛は、心から求める人には、どんな人でも感じることができる。
エゼキエルはダビデより四百年ほども後の人で、ここでは象徴的に本当の王が出るということを言っている。
…わたしは彼らの上にひとりの牧者を立てる。
…彼は彼らを養う。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。 主なるわたしは彼らの神となり、わがしもべダビデは彼らのうちにあって君主となる。 (23~24より)
ここで言われているダビデは王であた、後にあらわれるキリストのことを指し示すものとなっている。
新約聖書では、王なるキリストということも、とくにヨハネによる福音書で繰り返し現れる。
また、平和(シャーローム)についても述べられている。(25~31節)
聖書における「平和」は、一般的に言われるような「戦争」の反対語ではなく、「(神の恵みによって)完成、あるいは全うされた状態」という意味をもっている。
それゆえ、本当の意味のシャロームは、神(キリスト)から命の水をいただくことによって与えられる神の愛を受けて初めて生じる魂の平安である。
善き羊飼いは羊のために命を捨てる。主イエスは永遠の羊飼いで霊的な王であり、信じる者のただなかにいてくださる。
イエス・キリストが現れたゆえ、私たちがそのイエスを信じるときには、主がいかなるときも共にいてくださり、霊的に養ってくださる。
過去の歴史でどのようなことが起こっても、この真理は変わらなかったし、これからも変わることはない。
大震災でなくなった方々に関する新聞記事やニュース報道などで、しばしば見かける言葉が、「鎮魂」 ということである。「亡くなった人たちへの鎮魂の思いを詩に綴った」とか、「鎮魂の旅」、あるいは「鎮魂のための音楽会」などと繰り返しつかわれている。
しかし、たいていは、この言葉の本当の意味を知らずして用いられていると思われる。
以前、いのちのことば社から出された、ある高齢の有名なキリスト者の書いた文章に、この「鎮魂のために…」という言葉があったので、それはキリスト者として使うべきでないことを指摘したことがあった。出版社は、検討してみると言って1週間ほどのちに、やはりその通りであったと言って、今後の版では鎮魂という言葉を削除すると、電話があったことがある。
それほど、この言葉は、その意味を考えないで使われていることが多い。
「鎮」という漢字は、金属の重しというのが原意で、重みをかけて抑えるという意味を持つ。そこから、荒ぶるものをしずめる ということを意味する。それゆえ、鎮圧とは反乱や暴動を武力を使ってしずめることであるし、鎮火というのは、燃える激しい火の力をしずめることであり、鎮痛とは、人間を苦しめる痛みをしずめることである。また、鎮守という言葉のもとの意味は、軍がとどまって乱をしずめることである。(「仏教辞典」岩波書店などによる)
このように見てくれば、鎮魂とは、魂が乱れ、荒ぶるものになるのを重しをかけて鎮める、ということになる。魂がおとなしいよいものなら、鎮魂などということは必要がない。死後の魂が、荒ぶるもの、しずまらずに生きた人間に反抗的あるいはたたりをもたらすものとなるということがこの言葉の背後にある。だからこそ、そのような生きた人間に害を及ぼすことがないように、鎮めることが必要となり、それが鎮魂ということである。
すでに引用した岩波書店の仏教辞典には、鎮魂とは、「死者の霊をなだめ、鎮めること」とあり、「古くから死後の魂は、生き残った魂に危害を加えると信じられ、それを慰め供養する儀礼が行われた。」と説明されている。
このように、供養されてはじめて、死後の魂は生きている人たちに危害を加えることがないようになって、祖霊と一体となっていくと信じられた。
このように、死者の霊あるいは魂がどのようになっているのか全く分からないのに、勝手に、その魂を押さえつけたり、なだめたりしないと、生きている人間に危害を加える(たたってくる)などと信じるのは、死者全体をそのようなものとみなすことであり、死者に対してもよい思いどころか、とても有害なものとみなしていることになる。
聖書においては、死者のための祈りということは記されていない。
キリストの言葉にも、使徒パウロやほかの新約聖書のどの書物にも、死者がたたってくる、危害を加えてくるからなだめ、鎮めるなどということは全く記されていない。
ドイツの著名なキリスト教指導者であったブルームハルト(*)は、「死者のための祈り」という小文において、次のように書いている。
「…先祖のための祈りは止めなさい。というのは、それが正しいと言っている聖書の箇所はどこにもないからである。 死者がどんな状態であるかは、あなたは全く知らないのです。…まず自分の罪のことを考えなさい。罪は息絶えることを望んでいないのです。
ですから、生きている人のために祈らねばなりません。 死者は主の御手のうちにあります。
主の御名は、憐れみ深く、恵み深く、忍耐深く、大いなる恵みと真実に満ちている(出エジプト記34の6)ということで満足できるのです。」
(*)「悩める魂への慰め」64頁。ブルームハルト(1805年~1880年)著。新教出版社刊。ブルームハルトは、牧師として魂の救いのために働いたが、他方では特別ないやしの賜物を与えられていて、リューマチ、カリエス、肺結核、そして精神の病なども祈りによっていやした。スイスのカール・ヒルティもブルームハルトについてしばしば言及し、最もよく理解した人々として、キリスト、ヨハネ、ダンテ、トマス・ア・ケンピスなどと共に、彼の同時代の人々としては、カーライル、ブルームハルト、ブース夫人、トルストイなどをあげている。なお、このブルームハルトの息子、クリストフ・F・ブルームハルトも牧師であったが、彼の信仰は、神学者として有名な、バルトやブルンナーなどにも深い影響を与えたと言われている。
死者は、次の聖句にあるように、神の御前に置かれ、生前の心のあり方、言動、特に悔い改めがあったかどうかによって適切な裁きを受けるということである。
…言っておくが、人は、裁きの日には、責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、自分の言葉によって罪ある者とされる。(マタイ12の36)
… イエスは数多くの奇蹟の行われた町々が悔い改めなかったので、叱りはじめた。…お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、陰府にまで落とされるのだ。…(同11の20~24)
それは神の無限の英知と正義、そして愛に基づいてなされることであり、人間には分からない。私たちはただ神が死者を最善にしてくださると信じればよいことなのである。
表面的に神を信じないといっていても、死の近づく苦しみのとき、十字架でイエスと共に処刑された重罪人のように、その人は悔い改めて神を求めたかも知れず、また口では信仰的なことを話していても、心では真実に反する思いを抱き、神に立ち返ることもない場合(*)には、それらもすべて見通しておられる神が、いっさいを見た上で、裁きをされ、最善のことをなされるということなのである。
(*)私に向って主よ、主よ、という者が皆、天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入る。(マタイ7の21)私たちは、御心に添えなかったと感じたとき、すぐに主に立ち返り、赦しを受けることによって御心を行う者とみなしていただける。
聖書で繰り返し言われているのは、祈りは死者に対するものでなく、生きている人に対することなのである。
隣人を愛せよ、ということは、身近に接する人は誰でも真実な思いと祈りをもって接するようにということであり、たとえ敵対してくるものであっても、彼らがよくなるように祈りをもってせよ、ということであり、いつも祈れ、という言葉もみな、生きている人のために、彼らの魂が本当の幸いを得ることができるようにとの願いなのである。
このように、キリスト教は、万能かつ愛なる神を信じるゆえに、死者の魂の状態という、私たち人間には知ることのできないことに対しては神の愛にゆだねて信じるのであるから、死者については、祈ることを求められていないのである。
しかし、カトリックでは、死者の安らぎを祈る歌があり、それが、レクイエム(*)である。
(*)これはラテン語で、requiem と書くが、この語は 「安息、安らぎ」という意味の語 requies(レクイエース) の対格(英語の目的格に相当)である。re と quies(クィエース)から成る語であり、クイエースとは、安息、休憩という意味を持っている。
これが、英語にも入ってきて quiet(静かな)という語になっている。re は 再びというニュアンスをもった接頭語であるが、requies という言葉は quies(安息、静養)という語の強調形として使われている。
この語はもともと、ミサ曲の次の文に出てくる言葉である。
Requiem Aeternam Dona Eis Domine.
(レクイエム アエテルナム ドーナ エイース ドミネ)直訳すると、「安らぎを、永遠の、与えて下さい、彼らに、主よ」 、となる。「主よ、彼ら(死者)に永遠の安らぎを与えて下さい」という意味。この最初の語をとって、レクイエムというようになった。
レクイエムは、日本語では、「鎮魂歌」とか「鎮魂曲」のように訳されているが、この訳語では、すでに述べたことからわかるように、実はまちがった意味になってしまう。
本来のレクイエムには、死せる人々が生きている人に危害を加えるから、それをなだめるとかいう考えはまったくない。この言葉にあるのは、生きている人々と同様に、死者にも、最も大切なものである「主の平和(平安)」を与えて下さいという願いなのである。
主の平安は、主イエスがこの世を去るときに、信じる人に与えると約束されたものであり、神の持っている平安であり、最もよきものであるゆえに、生者、死者にたいしてもそのことを願うという気持ちから、カトリックではレクイエムという歌がある。
以上のように、キリスト教では鎮魂ということはあり得ないゆえに、レクイエムを鎮魂曲などと訳すのは本来は間違ったことなのである。
鎮魂とは、言い換えると、怨霊(おんりょう)を鎮めることにほかならない。
怨霊とは、自分が受けた苦しみや事故、災害などの運命を恨み、たたりをする死霊または生霊のことであり、生きている人に災いを与えるとして恐れられた。それを鎮めることを重要な任務とするために、さまざまの仏教、神道の複合した行事が行われることになった。
京都の祇園祭は、現在では観光で有名だが、そのもともとの起源は、京都に多くの病気―天然痘、マラリア、赤痢、インフルエンザなどが大流行した。その原因として、無実の罪を受けて苦しみつつ死んだ人の怨霊のたたりだとされ、その怨霊を鎮めるために始まったものである。このようなことが鎮魂ということの実態なのであるから、キリスト教とは全く関係のないことなのである。
それにもかかわらず、キリスト教音楽のミサ曲のなかのレクイエムを 鎮魂ミサなどと訳するのは、こうした歴史と実態を知らないゆえのことである。
このようなこととは別に、死んだ人の魂が恨んだり、うめいたり、悲しんでいるなどと勝ってに想像して、それを鎮めるために何かの音楽を聞かせるとか行事をする、ということは、死者に対してもその親族や友人に対しても適切な態度であろうか。
突然の死ではあっても、そのことを神が愛の御手によっていまは、最善になされている、と信じることこそ、望ましいことである。そのように、信じないなら、何十年経ってもやはり死者が悲しんで、恨んでいるなどと思うことになる。それでは、死者も生き残ったものにも、何一つよいことはないからである。
鎮魂という言葉とともによく使われてる「慰霊」という言葉も、やはり死後の魂は、悲しんだり、苦しんだり、憎んだりしているから、そのような霊を慰める、という考え方があるが、これも死後の魂を勝手に一律にそのような状態にいるとみなすことである。病気や高齢化で死ぬにしても、事故やその他の出来事で死ぬにしても、その魂は、生きていたときのあり方で神が適切になされる。真実なもの、神を見つめて生きたものは、事故や病気などどのような死に方であっても、その魂は地上のさまざまの苦しみや悲しみを終えて、神のもとで永遠の安らぎを与えられているであろうし、逆に悪しきことを意図的にしつづけたような魂は裁かれるであろう。一律にみな死後の魂が悲しんだり、苦しみや、憎しみを持っているから慰めるなどということは意味のないことである。
私たちにとって大切なことは、死者をそのように恨んでいるとか、憎しみを持っているなどと考えてその魂(怨霊)を鎮めようなどと考えることでなく、生きている間に神を信じ、神に立ち返り、死後はすべて神が最善にしてくださると、信じて生きることである。そのような魂には、生きているうちから慰めと力を与えて下さる。
そのことは、ヨハネ福音書で繰り返し強調されていることである。死後も、キリストと同じような栄光の姿になるのであるから、かえって地上の私たちを励ます存在としてあり続けることを信じることができるのである。
来信より
〇…今朝、録音(3月11日夜の天宝堂集会)を聴きかえして、とても恵みを受けました。
自民党が現在も、原発を推進しようとしていること、NHKも、表面的なことだけを報道して、事態の真相を報道せずにいることなどに危機感を覚えました。
NHKの情報だけなら、一般の人々は、原発の問題はほとんどないというような印象を持ってしまうと思います。
今朝も、福島沿岸でとれた魚の放射線量が下がっているという、ニュースを報道していました。
先ごろのEテレ(教育テレビ)で放送された「内村鑑三」に関する番組でも、キリストが力を与えて下さっているという、一番大切なことは、言われていないことを思っていました。
我々、信徒は、小さい存在かもしれませんが、テレビでは報じられない、神の力を証できる存在だと思いますし、証をしていきたいと思わされました。
昨夜の聖書箇所、コロサイ信徒への手紙2章10節の「あなたがたは、キリストにおいて満たされている。キリストはすべての支配や権威の頭である。」という言葉が印象に残りました。それとともに「キリストには変えられません」という賛美を思い出しました。
講話後半の内容では、イエスさまが罪のある自分を贖って下さった恵みを思いおこすことができて感謝しました。
「キリストの勝利の列」(コロサイ書2の15)になどに入るに値しない自分をも、その列にいれてくださる神様の深い恵みに感謝をしています。(関東地方の方)
〇大切ないのちの水が、点滴のように、一滴一滴霊に注がれていくような思いで読ませていただいています。受洗前の私にとって、聖書の解説はとても勉強になり、わかりやすく、教会とはまた違う受けいれやすさを感じております。(九州の方)
〇…いつもお世話になっております。息子が、再生するとき、よく誘われて聞かせてもらい霊の賜物を頂き感謝です。MP3版で聞けるのは本当にありがたいことです。(関西の方、MP3の再生とは、吉村孝雄の聖書講話シリーズCDのことです。)