いのちの水 2025年2月号 第768号
|
主をたたえよ 日々、私たちをにない、救われる神を。(詩編46の20) |
目次
・集会案内 |
イエスが十字架で処刑されるとき、最後まで従い、さらに墓に行き、安息日が終わった翌日の朝早く香料をもって墓にまで行く、そのように忠実に行なった人たちとは十二弟子たちではなかった。
十二弟子たちが、家庭も職業も捨ててイエスに従ったのは、特別に彼らの魂に働きかけたものがあったからだといえる。無数にいる人間のなかから、とくにわずか十二人だけ選ばれたという特別な招きがあった。
それにもかかわらず、彼らはイエスが捕らえられたときには、弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げてしまった。
(マルコ14の50、マタイ26の56)
その直前のイエスの必死の祈りにおいても、弟子たちは、みんな眠ってしまい、イエスが途中で起こしにきたが、それでもなお、再び眠ってしまったほどであった。
それゆえに、イエスが前夜は一睡もしないうえに、さらに兵士たちによって鞭打たれ、そのあげくに重い十字架を負わされてたくさんの人々のいる通りをわざわざ長い距離を歩かされた。 刑場に着いて両手、両足を、大きな釘で木に打ち込まれるという想像を絶する痛み、苦しみのとき、そばにいて祈りをもって見つめるべきであった弟子たちはそこにもいなかった。
そこにいたのは、婦人たちであった。とくに、四つの福音書のすべてに書かれてあるのが、マグダラのマリアである。
このマグダラのマリアについては、イエスの十字架での死、そして復活の時の双方において特に詳しく記されている。十字架の死とそれに続く復活こそは、キリスト教の中心であり、その二つの中心は、また世界史の長い流れのなかでも、最も大きな出来事であったといえる。
そのような特別な出来事にマグダラのマリアが深く結びつけられて記されていることに、その重要性がうかがえる。
書き方やその内容が、ほかの三つの福音書(共観福音書)と異なるヨハネ福音書においてもやはりマグダラのマリアのことは記されている。
しかも、共観福音書よりも詳しく記されている。
ほかの三つの福音書は、マグダラのマリアがイエスの葬られた墓にいったのは、明け方(早く)という表現であるが、ヨハネ福音書は、さらに、まだ暗いうちに、という語があり、「週のはじめの日、朝はやく、まだ暗いうちに、」と、より詳しくなっている。
そして、共観福音書ではマグダラのマリアはほかの一、二の婦人たちとともに、イエスのおさめられた墓まで来たところ、墓の入口に大きな石でふたをされていたが、その石が転がされてあり、そこに天使が現れてイエスが復活したことを、マグダラのマリアたちに告げたと記されている。
しかし、ヨハネ福音書では、とくにマグダラのマリア一人に焦点が当てられているが、女性が、遺体をおさめた墓に暗いうちから出かけていくということは、よほどの思いがなければそのようなことはしないであろう。
新約聖書において、マグダラのマリアについては、 なぜこのような特別に記されているのであろうか。
そのマグダラのマリアとは、どういう人物なのか。
…イエスは神の国を宣べ伝え、その福音を告げ知らせながら、町や村を巡って旅を続けられた。十二人も一緒だった。… 七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、…そのほか多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは、自分の持ち物を出し合って、一行に奉仕していた。 (ルカ八・1~3)
これが、イエスの十字架と復活のとき以外のマグダラのマリア(*)に関する唯一の記述である。
わずか一言であるが、この短いことばの中に、彼女がどのような人であったかが示されている。
七つの悪霊とは何か。それは七という数字は一種の象徴的な数(**)であり、完全、十分な といったニュアンスがあり、聖書では多く用いられている。
霊は風のようなものであり、数えられないものであるから、この表現はこの女性が徹底的に悪の霊のはたらきによって支配されていたということを暗示している。
(*)マグダラとは、地名であり、ガリラヤ湖の西岸で現在では、ミグダルといわれ、同じく西岸にあるティベリウスの北方5キロほどのところにある。
なお、このマグダラのマリアは後に聖人とされ、マグダラ は彼女の名前の簡略形ともなり、後の時代に女性の名前として用いられた。その名前のある女性が、帆立貝を用いた菓子を作ったのが広く伝わり、その菓子の名前が マドレーヌとなった。
なお、マグダラのマリアを、汚れた罪を犯した女とみなす説明がなされることがあり、絵画にもその解釈で描かれたものがある。しかし、このマグダラのマリアとは別の女性である。それは、ルカ福音書の7の36~49節の罪の女の記述の直後に、マグダラのマリアのことが記されているが、そこでは、罪の女であることなどまったく触れていない。
さらに、マルタとマリアは、ベタニアの人とあり(ヨハネ11の1、18節)、そのマリアはルカ福音書の罪の女が「主に香油を塗って髪の毛で足をぬぐった女」と、ヨハネ福音書ではとくに記されている。(ヨハネ11の1~2)
聖書で罪の女とされているのは、マグダラのマリアでなく、ベタニアのマリアである。
(**)…創世記に、第7日に、創造のわざを完成された、そのためその日を、他の日と分けて安息の日としたこと(創世記2の2~3節)、また、イエスは、七つのパンを取り…(ルカ8の6)、五つのパンと二匹の魚の記述(マタイ14の19)も5+2=7であり、また、「…人々は皆、食べて満腹した。残ったパンの屑を集めると、七つの篭いっぱいになった。」(マタイ15の37)…。
これらの個所からは、七という数に「完成、完全、十分な」という意味が含まれているのがわかる。
聖書には、ほかに悪の霊に支配されていた人の状況が書かれてある箇所がある。
…イエスが舟から上がられるとすぐに、汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやって来た。
この人は墓場を住まいとしており、もはやだれも、鎖を用いてさえつなぎとめておくことはできなかった。これまでにも度々足枷や鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足枷は砕いてしまい、だれも彼を縛っておくことはできなかったのである。
彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ちたたいたりしていた。
(マルコ五・2~5より)
このようなひどい状況であったが、主イエスはこの人から目に見えない悪の力を追いだして、その闇の支配から救い出されたのである。
マグダラのマリアもおそらくはこのような恐ろしい闇の力に支配され、絶望的な状態であったと考えられる。彼女はどうにも救いようのない精神の重い病気とみなされてしまっていただろう。
悪の霊は、暴力や詐欺などとして働くゆえに、そうした悪事、不正なことにも関わったかもしれない。
しかし、主イエスはそのような闇のただなかに置かれて苦しめられている人をも救い出すことができた。この女性はこのような七つの悪の霊に支配されるまでに、どのようないきさつがあったのか記されていない。
何か特別に苦しいこと、悲しみに打ち倒されることがあったかも知れないし、また大きな誘惑に負けて悪の力に支配されるようになったのかも知れない。いずれにしても、そうした絶望的状態になるまで、家族や周囲の人たちは何とかしてその泥沼のような状態から抜け出ることができるようにと祈り願ってきただろうし、可能な方法をいろいろと試しただろう。
しかし、家族も医者も人格のすぐれた人も指導者もすべてどうすることもできなかった。
そのようなとき、マグダラのマリアは主イエスと出会ったのである。そして長い地獄の苦しみから解放されたのであった。
人はだれでも罪深いものであるが、このマリアも悪の力によってさまざまの悪しきこと、罪を犯してきたことであろうが、主によってそうした罪を赦していただいたことが推察される。
主イエスが言われたように、多く愛するのは、多く赦されたからである。
次の言葉は、ベタニアのマリアに対して言われた言葉であるが、これは誰にでもあてはまる真理として言われている。
…この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない。」 (ルカ七・47)
マグダラのマリアがほかの弟子たちすら恐れて逃げてしまっていたなかで、恐ろしい苦しみから死を迎えようとしていたイエスを最後までその苦しみを共にに担うべく、処刑されている十字架の近くまできて、最後まで見つめていたのであった。
このように、自分を絶望の淵から救い出してくれた主イエスへの感謝と真実な心、そして愛によって行動したのがマグダラのマリアであった。
主イエスへの愛、それは神への愛と同じものであって、イエスがまず神を愛せよ、といわれたことを思いださせる。このように真実にイエスを愛するものには、求めよ、さらば与えられる、という約束の言葉の通り、復活のイエスからの直接の語りかけを受けて、顔と顔を合わせて見るという大きな幸いを与えられ、それによって復活の力が与えられたのが推察できる。
しかし、彼女は復活したキリストがすぐそばに立っているのを見てもなお、それがイエスだとは分からなかった。ヨハネ福音書では、マグダラのマリアが復活のイエスに直接語りかけられたときの状況が次のように記されている。
…マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、白い衣を着た二人の天使が見えた。
天使たちが、「婦人よ、なぜ泣いているのか」と言うと、マリアは言った。「私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません。」
こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それでもなお、それがイエスだとは分からなかった。
イエスは言われた。「婦人よ、なぜ泣いているのか。だれを捜しているのか。」マリアは、園丁だと思って言った。「あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が、あの方を引き取ります。」
イエスが、「マリア」と言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語で、「ラボニ」(*)と言った。「私のラビ(教師、先生)」という意味である。(ヨハネ福音書二〇・11~16)
(*)日本では、「先生」という呼称は、議員や教育関係すべて、また医者や弁護士等々、いろいろな職業の人に使うが、この個所で「先生」と訳されているラビというのは、旧約聖書の真理を教える教師であり、神の言葉を教え導く聖職者という意味で用いる。
復活したイエスと出会ってもなおそれがイエスであるとは分からなかったが、イエスの「マリア!」という呼びかけのひと言で彼女の目は開かれて、復活のイエスと知ったのである。そしてこれが、歴史上の最大の出来事ともいえるキリストの復活を初めて知らされた瞬間であった。
生きた主からの呼びかけが、決定的だった。
これは、パウロにおいても同様である。パウロはユダヤ教(律法)のすぐれた教師であったガマリエルに特別に学んだほど、ユダヤ教の経典たる旧約聖書を深く学んでいた。しかし、イエスがその旧約聖書の指し示す人物であることはまったくわからず、かえって、キリスト教をモーセ律法に従わないものとして憎み、キリスト者を殺すことさえし、国外までキリスト者を捕らえるために出向くほど、全力あげて迫害した。
また、律法(旧約聖書のとくにはじめの部分の5書を意味する)の学者たちも、イエスの語ることを聞いても、その驚くべき言動、奇跡を見てもなお、ユダヤ教の学問は、真理を指し示すことにはならなかったのだった。
そのようなかたくななパウロを根本的に転換してキリストを信じるようになったのは、学問でなく、また経験でもなく、説教などでもなかった。
それは復活して生きて働くキリストの光が注がれ、キリストがパウロに直接に語りかけたからであった。
それほど、生きたキリストからの語りかけは重要なのである。
ペテロやヨハネ、ヤコブといった代表的な弟子たちもまた、ユダヤ教の経典たる旧約聖書を学んだのでもなく、模範的な信仰者の言動に接したこともなかった。漁師というしばしば夜間も働く厳しい労働条件にあったゆえに、書物もなく、それゆえ文字も読めなかったであろうと推察されている。
そのような彼らがイエスを救い主として信じるようになったのは何故か。
それは、だれかに教わったからでなく、説得や模範でなく、次のように直接のイエスによる語りかけであった。
…「私について来なさい。…」とイエスが言うと、二人はすぐに網を捨てて従った。(マタイ4の19~20)
イエスからのひと言は、職業や家庭をも捨てさせるほどの驚くべき力を持っていたのである。
マグダラのマリアは、イエスの12弟子たちと同様に、イエスが復活するなど、全く信じたことはなかった。
しかし、マリアは、イエスへの、またイエスの背後におられる神への真実な愛をもっていた。そのような愛こそは、最も復活のイエスに近づくことを与えられるのである。
知識や学問、血筋や生まれつきの能力、また長い人生経験…等々が全くなくとも、ただ主イエスを愛し、神を愛するという真実な心があるときには、神は近づいて下さるということをマグダラのマリアの記事は示している。
そして、悪の霊にまったく支配されていたときには、周囲の人たちからも嫌われ、見下され、差別を受けて、だれからも相手にしてもらえなかったであろう。
孤独と苦しみ、淋しさ、そして悲しみ等々、言うに言えない闇のなかにあって呻いていた魂がそこから救い出された、ということ、それは天で大きな喜びがあったと考えられる。そうした苦しみの根源に赦されない罪があったであろう。
中風で寝たきりの人を友人たちが運んできて、どうしてもたくさんの人々がいてイエスの前に行けないために、その家の屋根の一部をもはいで病人をつり下ろすという非常手段を用いて、イエスのまえに出ていったとき、イエスは友人たちの信仰を見て、病人に「あなたの罪は赦された」と言われたことがあった。
(ルカ5の18~20)
病気の重い苦しみに対しても、罪の赦しが与えられることが、根本的に重要なこととされている。
…一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。」(ルカ福音書十五章10)
悪霊の力から解放される、というようなことは現代の私たちとは関係のないようなこととして受け取られることが多い。
悪霊という訳語からは、何か幽霊とか亡霊のような、人間に悪しきことをする霊を連想することが多いが、目に見えない悪の力である。 私たちを取り巻く闇の力から解放されることこそ救いである。
また私たちの内に潜む自分中心の思いもまた悪しき霊(悪の力)の支配ゆえである。私たちのそうした罪をすべて見抜いておられる神がその罪を赦してくださる、ということは悪の力に勝利することであり、救われるということである。
そしてそれこそ、人間の新たな歩みの出発点となるのだということがマグダラのマリアについて新約聖書で、特別に重要なこととして記されている理由なのである。
イエスの遺体を納めた墓といっても日本のような石を積んだものでなく、石灰岩の岩場をくり抜いた横穴のようなものであり、そこに大きな石でふさいであった。そのような状況なら、わざわざ朝早く出向いてもなにもできないにもかかわらず、それでもマグダラのマリアは イエスの遺骨がおさめられたその墓の場所に出向いた。
どうせ大きな石がおいてあるのだから、死者に香油など塗ることもできず、何もできない、といって行かないのでなく、たとえそこに入れずとも、すぐ近くまで行って祈りを捧げ、主イエスからうけた悪霊からの解放、罪の赦しを感謝しようとしたのだった。
そのように、愛とは計算をしない。
目に見える結果があるかないかは問題とせず、主の愛が導くままに、祈りをもって可能なことを精一杯することなのである。
そして、そのような魂の姿勢に、そこから復活という最大のことを誰よりもさきに知らされて、復活の主と出会うという恵みが与えられた。
それは「弱きところに神の力が現れる」という使徒パウロの有名な言葉を思い起こさせるものである。
神、そして復活した活けるキリストは、人間世界にいつの時代にも存在する暗い世界ー悪霊が暗躍する状況における人間を見つめて下さっているのであり、主の愛のまなざしはどんな闇をも見通し、そのなかで真剣に求めるものに聖なる霊ー神の愛を注いで下さっているのであり、それゆえに、神は愛なり、と言われている。
![]() 万軍の主はわれらの砦
万軍の主はわれらの砦
詩編46篇
今日の所は詩編の46篇を何度かに分けてきましたが、最後の所ですね。この詩はルターによって宗教改革がなされたとき、ルターがこの詩にまさに自分のことが言われている、と感じて、この詩をもとにして、「神はわがやぐら」という讃美歌を作詩、作曲したことで知られています。
そして今日に至るまで広く用いられています。これはルターによるキリスト教世界の大いなる改革の、霊的な進軍ラッパのようなものとなったのでした。
この詩編46篇という短い詩に「万軍の主は我らと共に」、とか、長く用いられてきた口語訳にある「神はわがやぐら」といった訳文は、現在の私たちにおいては、とてもなじみにくい言葉です。
それでその後の新共同訳や聖書協会共同訳では やぐら を「砦」と訳しています。これは、原文のドイツ語でも Burg なので、砦と訳するのがふさわしいことです。この詩をもとにした讃美歌267では、「神はわがやぐら」と訳していますが、やぐら といえば、現代では、やぐらこたつとか、火の見やぐら といったことが思いだされる人が大多数であり、この訳語は適切とはいいがたいものとなっています。
この詩編46の最後の部分に、「万軍の主は我らとともに」とか「ヤコブの神は、我らの砦の塔」という言葉で締めくくられています。
しかし、ヤコブの神とか万軍の主というのは、おそらく大部分の日本人にとっては何のことかわからないと思われるし、。万軍の主という言葉はキリスト者にとっても分かりにくいものです。
なぜヤコブの神と言うのか、我々と関係のない特定の昔の人間の神なのか、我々の神なのに…、そういう疑問も起こったりして詩編や旧約聖書全体にもそういうところもいろいろ出てきますが、初めて読んだ時あるいは何度読んでもなんらかの説明がなければ意味不明ということが沢山あるわけです。これは書かれたのが、二五〇〇年以上も昔と考えられているので、当然そういうことも起こりうるわけです。
万軍の主とは
万軍とありますが、ヘブル語では「ヤーヴェ ツァバーオース」といいます。ツァバーオースのもとの形は、ツァーバー(サーバー)というのですが、これは「万象」とも訳されます。
創世記の2章で天地万物と訳され、また、万象とも訳されている原語は、 サーバーとですが、それが万軍とも訳される。
このサーバーとい言葉は、聖書では多く用いられています。新改訳では「天と地とその万象が完成された」と訳されています。万象というのは、あらゆるものを指していう言葉です。天地と全ての物が完成した、そういうようにサーバーという言葉とヤーウェという二つの言葉が、「万軍の主」と訳されています。
このサーバーは、「万象」と訳されたり、実際の、イスラエルの軍勢を意味することもあります。
この重要な詩編で二回も繰り返されてるのはどういうことなのか。
これは初めて読んだときには、不可解です。しかもこれが旧約聖書では実に多く用いられている重要な語となっています。
特に預言書に非常に多い。一番多いのはエレミヤ書 ゼカリヤ書 イザヤ書 その三つが非常に多いわけです。どうしてだろうかということもあります。具体的にいえばエレミヤ書では
94回もこの万軍の主という言葉が出てくるんですね。イザヤ書も68回も出てくる。ゼカリヤ書も78回もわずか15頁ほどの中に用いられている。
旧約聖書全体で万軍の主と訳される原語は332回も使われておる。それほど旧約聖書の人々とくに預言者にとっては非常に重要な内容を持っていたということが分かるわけです。
それだけ沢山使われているけれども我々にとってはほんとに意味不明の様に見えるわけですね。これどうしてなのだろうか。すでに触れたように、実際にこのイスラエルも全軍を指して使われてる所もあります。
それから森羅万象、万物を意味するけれど、とくに天体、星々をも意味することがあります。
星々は特にローマ時代の有名な哲学者であったエピクテートスがいます。ヒルティが幸福論の第1巻の中にエピクテートス語録をそのまま載せているぐらいヒルティも共感して哲学的なものに慣れてない人にもということでそのように重要視されています。そのエピクテートスは奴隷であって、身体に障がいもあった。それでも後に解放奴隷になった。奴隷であった人がそういう2千年でも残るような叡知に満ちた著作を残している。その中に、星々は目に見える神々だと記しています。
星というのは永遠性 人間に一切汚されない いかなる事態が日常に起ころうともまったく変わらない光 輝きを持っている。そして星の仲間である月や太陽は完全な円形にみえる。
肉眼で見て完全な円型をしたものが何千年も続くというものは地上にはどこにもないです。
月や太陽以外。そういう風に星々月も含めて、地上にはありえない完全性、永遠性、一切汚されないそういうものを持ってると感じられたればこそ2千年も前のローマの重要な哲学者であったエピクテートスは目に見える神々だと言っています。
星々はそのように、特別な意味を持って語りかけていたのがうかがえます。
現代人は科学的にみるだけの人々が圧倒的に多い。星までの距離が何光年 何億光年、銀河系にはどれだけ沢山の星があるかということ、太陽のあの莫大なエネルギーは、核融合による。水素の原子核が核融合して莫大なエネルギーを出す、それを地上で科学技術の極めて高度なものとして造られたのが水素爆弾だ。
しかし、聖書の世界、実際に存在する目に見えない世界を深く感じる賜物が与えられるときには、そのような科学的な知識とまったく別な真理を汲み取ることができる。
イエス・キリストの誕生のときに、東方の博士たちは、星に導かれて博士たちがイエスのもとに来ることができた。
また、聖書の最後の黙示録にも明けの明星はイエスキリストを指し示すと記されています。金星ですね。そのように非常に重要なものとして星を位置づけているのがすぐに分かるところです。
それから、詩人、詩を作る人は世界中に数知れずおるわけですね。自分の思ったあるいは感じたことを短い言葉でしかも美しい表現で書き記したものを詩と言われて、日本では和歌、短歌、俳句などが詩の領域に入るわけです。
その詩の世界でもっとも広大で科学技術も政治も文学的なことも人間の愛情も罪も宗教家の腐敗や国家社会の争い、そして音楽、讃美の果たす役割、罪の裁きの厳しさ、重大さが記され、そこから悔い改めの重要性にも触れている… そういう人間世界のありとあらゆる様相を整然としたリズムと3行ごとに韻を踏むという厳密な構成となっている1万四千行ほどにも及ぶ世界に比類のない詩、それがダンテの神曲 Divine Comedyです。聖なる喜ばしい劇、最終的には喜ばしい内容だからそういう書名となっています。
ダンテ神曲にある地獄篇、煉獄篇、天国篇の最後に、stelle 星という言葉をおいています。
それぐらい星は注目を集めてきたわけです。あの有名なカントも何度振り返ってみても心に新たな感動を呼び起こすことが二つある、その一つは、心の深いところで、善きことと悪しきことを直感的に人間だけが感じるーそれはいわば星のようなものが刻まれている。しかも永遠的ですね。人を騙したり嘘をついたらどこか心に不快な思い 暗い思いを持つようになっている。
他方、人に善きことをすればどこか喜ばしい。人には、美しい物を直感する能力がある。動物にはないですね。美しい花に見とれる猿 美しい花に見とれる犬 どこにもいないわけです。人間の中には深い真理に対する直感力がある。また悪に対しても必ず裁かれる、だから人を殺してはいけないなんていうことを忘れたから殺した、人の物を盗んではならないということを忘れたから盗んだ、そんなことはだれも言わない。
それぐらい深く刻まれたそういうような善悪 美しさ、そういう風な判断力があると、それはほんとに不思議な神秘なことだと…。
それともう一つ目に見える世界では星のちりばめられた天空、それは何度見ても新たな感動を覚えずにいられないとカントがその著作の中でも言ってるところです。
聖書で現れる「万軍の主」というとき、その万軍は、天の星々という意味を含んでいるのです。全ての星々がいわば神のもとにあり、神とともに悪と戦う存在なのだと。
さらには、万象、ありとあらゆるもの、それも実は神が創造したゆえに現在も万物を支配し、また支えており(ヘブル書1の3)、それゆえに、それらの自然のものもまた、神がその御計画に応じて、それらをも悪の力と戦う道具とされるということなのです。
非常に壮大な内容を讃えておるというわけですね。だからあの捕囚になる時に、ユダヤが滅びたが、エジプトの助けに頼らずに、遠いバビロンへ逃れて行けば救われる、ということでバビロンへ行けとエレミヤ自身が受けたから、そしたらあれは売国奴だと、そんな外国へ降伏してはるばる遠い道を行くのが救いの道だなどと屈辱的なことを言う、ただでさえ、エジプト大国の攻撃を受けて大混乱のなかにあるユダヤの人々をさらに惑わす人間だとされ、エレミヤはそのために殺されそうになります。井戸の中へ放り込まれる。
そしてまたエレミヤ自身は助かるためにバビロンにもいかず、かえって、エジプトを頼って逃れていく人々とともにエジプトへ行き、そこで殺されたと伝えられています。
そのような亡国の民となるという国家国民がもっとも苦難に直面したその一番困難な時、エレミヤは命がけで神の言葉ー真理を伝えたのです。
そのエレミヤ書に、「万軍の主」という言葉が最も多く用いられています。そのような大混乱の時代にもっとも神の言葉を持って、その当時の世界の大きな風潮ですね、ユダヤ人全体に立ち込めたエジプトに頼ろう 逃げて行こう、それに抗して御言葉を語った彼にとっては一人であるようだけれども万軍の主という言葉をそれだけ沢山使っているということは全能の神は滅びゆく民をも決して見捨てない、彼らのためにあらゆるものを用いて悪の力と戦い、民を導こうとされているのだ、全てを用いて戦っておられるんだ、そういうような深い直感があったということです。
それゆえに万軍の主という言葉は、預言書イザヤも非常に多く使っているわけです。預言者というのは時の様々な不正なことに関して神の言葉を一人ででも語るというような特別な力を持った、与えられた人たちだったんですね。
武力でなくて神の言葉によって戦うということです。これは、新約聖書のエペソとしては私たちの武器は目に見えないものなのだ。霊の武器だ。信仰、それから神の言葉、それから聖霊だ、それから足にはく履物、履物が切れたら痛くて歩けない。履物は非常に大事なんですけれども、履物として福音を備える。そういうことが言われてることですね。
万軍の主こそ我々と共にいてくださり全てのことを従えて悪の力と戦ってくださる主がおられるんだ、そういうことで苦難の時に、46篇2節、どんなことがあっても私たちの避けどころとして老年となって死が近くなっても、病気であっても事故、災害、戦争…等々、いかなることがあっても、主に立ち帰り、そこで私たちが主にすがることによって神が砦となって悪の力から防いでくれると、苦難の時そこに必ずいてくださるというこのことが8節、「万軍の主は私たちと共にいて守ってくださる、どんなことがあっても助けてくださる、それは万軍、全てのものを天使たちー当時の人々にとって神のごとき永遠の存在たる星々を従えて悪の力と戦んてくださるのだと信じていたのです。そういう風にこの万軍の主っていうのは悪の力と戦ってくださる神様なんだと言おうとしています。
この世は悪で満ちている、昔からずっとそうだったわけです。今もそれがいっそう、スマホにしてもテレビにしても頻繁に悪の力ばかりが宣伝されているぐらいに、かつてこんなことはなかったです。毎日毎日そんな宣伝がされているかのように、悪事、犯罪等々が大量に報道される。そのようなことをすると、悪の力はこんな大きい、こんな犯罪があると、トランプが何をしかけるかわからん、場合によっては核でも使うかもしれんぞ、プーチンもそうだ、ヨーロッパ諸国も黙っておれないと、だんだん分裂もひどくなってどうなるか、行く先どうなるか世界で誰一人経済学者も政治学者もノーベル学者も誰一人はっきりした予見はできないわけです。
でも神は、はるかな昔からいかなることがあっても必ずそこにいて真理に着こうとする者を助けてくださる。そして最終的には全能だからこそそれらの悪の力を根絶するんだ。全能で真実で愛の神でなかったらそんなことはありえないことです。
神は万物を創造された、ということは、太陽やあの無数の星さえ創造した。一方小さいミクロでは大腸菌の様に千分の1ミリの中に千個もならぶほどの微少なものだが、それらもその内でなされる膨大な化学反応も、やはり神がその根源となる化学法則を造ったゆえである。
身近な火が燃えるという現象も、何かのものの内に炭素原子を含む物質があったら十分な熱を与えてやれば、その炭素と空気中の酸素が反応して二酸化炭素となる、そういう法則もまた神が作った。そういう全能の神だからこそこの全世界も神が支え、最善の状況へと導こうとされています。
この世界に、人間だけを見たらどこまでも信頼できる人間などいないのです。キリスト者と言えどもペテロの例であるように3年間もキリストに従って家族も捨てたような人であってもなお、いざというときには大きな嘘をついてしまったんですね。
3年間もいっしょにいて、数々の奇跡、また誰も語ったことなき真理を直接に聞いていた弟子であるのに、イエスの逮捕後に、女中から、「あなたもあのイエスの仲間だった」と言われて、そんな人は全く知らない、と呪いの言葉さえ出して強く否定した。
権力も地位もない女中に言われたときに狼狽して偽りを行ってしまうほど人間はほんとに信頼できない弱く醜い存在なのだと記しているのです。
だからこそ私たちは人間でなく、万物を創造し、いまも万物を支え、導く神を信じる。そのような神を信じるときには、悪しき人に対しても、憎んだり、忌避したり、軽蔑したりするのでなく、神の力が働くならば、祈っておれば時が来たらきっとその人も変えてくださるだろうという信頼を持つことができるのであって人間そのものを信頼せよとは聖書のどこにも書いてないです。
そういうわけでこの万軍の主というのは最初のことと繋がっているわけです。苦難の時どんなことがあっても助けてくれる。何物をも神の共労者として用いるということですね。
苦しいとき、今ただちに神が私たちを助けてくれるということがないことも多い。しかし、ずっと遥か昔からそのようなことは神様の大きなご計画でほんとうに求める人は必ずどんなことがあっても助けてくれる。人間は砦にはならない。人間は崩れてしまう。神様をしっかり信じていてもなお、著しい苦難のときには、動揺することはある。
神様などはいないのでないか、というほど絶望的になることがあってもー主イエスさえそうだったーそれでもなお神様を信じ切っていくならばほんとうにそこから超えて大きな光 力を与えられて歩んでいくことができると しかも最終的には殺されたらどうするのか、殺されたら神様の万能、全能の力によって輝かしいキリストの栄光の姿の様に永遠の命を持った存在として神の御許でもはや闇も押し寄せない所で存在することとなるということです。
この詩編46篇の9節に、「主の成し遂げられることを仰ぎ見よう」と訳されていますが、原文は、「来たれ、見よ」となっています。
この個所は、英語訳では、Come, behold、あるいは、Come and see the works of the Lord.です。
聖書の内容は、常に確信をもって記されているということです。聖書の世界ではこのごろ多用される~かな、といったあいまいな言い方をしないのです。正しいことは正しい、良いことはよい、ほんとの神がおるならおると、命懸けでそういうことを守ってきたのが聖書の民だったんですね。この「来たれ、見よ」という呼びかけの中に含まれる「見る」ということの重要性はヨハネの福音書の1章の所で繰り返し強調したことでした。
黙って机に座って本を読んで考えるだけでは、物事の重要な部分が分からない。実際に人に会う、その場そこに祈りをもって行って見ると、初めて、そこで生じるいろいろなことを通して、主イエスが現在も生きて働いておられることが実際に体験できる。
ヨハネ福音書1章は特に霊的な象徴的な表現がいっぱいです。1章29節、洗礼のヨハネが「私は水で洗礼を授ける、だがイエスは聖霊による洗礼を授ける」のだと語った、その翌日洗礼のヨハネは自分の方へイエスが来るのを見た。そして「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ。」
「見よ、神の小羊を」これが原文の表現です。そして、その人は世の罪を取り除くんだと。神の小羊、殺されて血を流して捧げられる。しかもそれは罪を取り除く、身代わりになってという最大の霊的なことを行う人だと、全世界の罪を取り除く。そして血を流してまで神に捧げられる。私たちの見るべきものはこの世の地位の高い人、有名な俳優やスポーツマンじゃない。
我々が本当に見るべきはイエス・キリストである。この一言にあるように、私たちの罪を担って取り除いてくださる、しかも自ら殺されて血を流すまで苦しんだ神に捧げられたイエス・キリストなのだと。
ヨハネはまた36節でも「見よ 神の小羊だ」と言いましたが二人の弟子はそれを聞いてキリストを指し示す言葉を聞いただけでイエスに従った。それぐらい神の小羊を見ることが大事なんだということを言おうとしてるわけです。
「来たれ、そして見よ」 実際にイエスの所へ言ったら分かると、どういうところに留まるか、これもそうなんですね。家にどこに泊まるかという表面的なことを問うているのではないのです。
ヨハネ1章46節、ナタナエルに出会った。ナタナエルがナザレ、あんな田舎から何か良いものが出るだろうか、出ない でるはずがないと言ったんですね。そしたらフィリポは「来たれ、見よ」と勧めた。
我々は先ず人間を見ようとする。けど、その人間が優れた人であるほど背後でその優れたものを与えた神を見つめないといけないのに、あの人は素晴らしいとか言ってその人を褒めたたえてしまう。
特にスポーツなど、その最たるものです。そういう特別な能力を与えたのは神であるのに彼が努力したんだ。努力も神が与えてなければないまま。例えば寝たきりの人は決してホームランを打ったりできないわけです。神がそういう健康も与えて頑張る力も神が与えたわけです。求める力も与え大脳の働きも正常だったからこそ求めたわけです。その大脳全体も神様が与えたのです。ですから、「来たりて見よ」、ということは霊的な意味を含みつつ、いろいろなところで出てきています。
聖書共同訳では、「来て、主のわざを見よ、主は驚くべきことをこの地に行われる。」
そして11節、新共同訳では「力を捨てて知れ」となっています。
しかし、口語訳は「静まって私こそ神であることを知れ。」以前の口語訳はそうなんです。その訳が原文でも前後関係からしても当然望ましいということからさっき言ったような代表的な訳も be still(静まれ!) と訳されています。
そしてこの詩の最後に 再度確信を証しして、「万軍の主(全てのものを支配されているとともに、万物をも用いて悪の力と戦う主)なのだ、永遠の主なのだ、そういう主が私たちと共にいるなら恐れる必要はないと。代々ずっと神に選ばれた人たちが信じてきた神こそが私たちのほんとの砦なんだ、人間ではない、武器弾薬ではないということをもう一度念を押して、神からうけた確信だとして語っているのです。
現代のマスコミー新聞、テレビ、ネットニュース、…等々にしても批評家 評論家皆いろんなことを言うけれども聖書の内容には全く触れない。聖書にこそ、永遠に変わらない根本に真理があるにもかかわらず…。
そのために、最近は、日本は憲法9条という貴重なものが存在してきたにもかかわらず、その精神を守ろうとする人たちの声は新聞やテレビ、その他のマスコミなどでもあまりみられない。アジア、太平洋戦争によっておびただしい人々を犠牲にしたゆえに与えられたのであるから、その憲法9条を尊重し、軍備は持たないで話し合い、平和 あるいはいろんな困難な所に海外協力隊を作って各地に派遣する。
そういうことを常に続けている国を他国が攻撃しようとするであろうか。もしも、攻撃されることがあろうとも、武力を持って報復攻撃ー戦争となる道ーをしないで、全力をあげあらゆる手段を通して平和的な話し合いをするということこそが、大量殺人、破壊、そして周囲の国々にもたいへんな混乱やあらたな戦争を引き起こすに至らない道です。
そしてとくにキリスト者にとって、私たちの本当の国は目にみえる国ー日本ではなくて、目に見えない天の国こそ私たちの国です。日本の国だってもともと、東北から北海道には、アイヌの人々が住んでいたのを、武力で攻撃して追い出していったのでした。沖縄だって琉球王国として450年ほど続いていた国であったのを、1879年に日本の領土に組み込んだのでした。
このように、国境というのは世界で見ても、さまざまに変化しているわけです。国もなくなったり、国の境が大きく武力などで変更されるということは常に生じてきたことです。
そういうことを大きな視野で考えればこそ主イエスは、次のように言われたのでした。
…私の国は、この世には属していない。もし、私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように、部下が戦ったことだろう。しかし、実際、私の国はこの世には属していない。」(ヨハネ18の36)
これと同様なこと、私たちが属する家族と、本当の家族については次のように言われた。
…イエスは、「私の母、私の兄弟とはだれか」と答え、周りに座っている人々を見回して言われた。「見なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。」(マルコ3の33~35)
イエスの言われた神の国こそは、目にみえる領土も人間の統治でもなく、いかなる武力の攻撃や自分中心、自国中心の政治家があらわれようとも、決して侵略されることなき国です。
しかも、その神の国を統治するのは、愛と真実の神、キリストであるゆえに、いつまでも変ることがないし、いかなる弱い人も、罪深きことを犯してきた人であっても、ただ、そのような神を信じるだけで、その神の国の民とされるのです。
それゆえに、そこでは、祈りという神と人との霊的交流が、共通の霊的言葉となります。言語の障害もない国です。
こうした清く永遠的な神の国に入れられ、そこでいのちの水を飲み、聖なる風を受けるようになるなら、それこそが、もっとも根本的に武力による戦い、戦争を起こさないことにつながると感じます。
そしてそのような神の国に入るためには、健康、病気、能力などにかかわりなく、老若男女年齢にも関わりなく、主を信じて仰ぎ見る、ということだけです。
そしてこうした神の国に入ることを赦された人は、決して暴力(武力、大量殺傷、大量破壊たる戦争)によって物事を解決しようとは思わなくなります。
このような神の国こそ、現在のような国を守ると称して、夥しい人々の命が失われ、また大量の難民を生み出し、またその家族も筆舌に尽くしがたい苦しみや悲しみを持ちつつ生きている人たちをおびただしく生み出す戦争を推進する心には決してならないと思われます。
イエスの言われた神の国が、一人一人の心に与えられるとき、そこに、主の平和が宿り、それこそが、本当の平和の礎となるのがわかります。
(2025年2月4日 夕拝にて)
主を畏れ、心を尽くし、真実をもって主に仕えよ。
そして、主がいかに大いなることをしてくださったかを悟れ。(旧約聖書 サムエル記上12の24)
私たちの生きる過程では、様々な状況で出会う苦しみや悲しみー病気、事故、災害、戦争、人間関係等々、あらゆる種類の苦しみに関して、人々を襲う無力感や、絶望的な苦悩がある。
そのような長い苦しみの後で、神からの語りかけによって自らの傲慢さに気づき、神への方向転換を与えられ、苦難からのそして、罪からの救いに入れられる。 そして、すべてが取り上げられたと思っていた自分に、神は苦難を通して失ったものにはるかに勝る祝福を注がれることに気づかされる。
神様がどんなに大きなことをしてくださったかそれは苦しみの最中にはわからないけれども、時が過ぎ、また御心にかなった時において、軽く見過ごしてきた事の中に深い神の愛があったことに気付かされ、もはや取り返しがつかないことであっても、それをも赦してくださるという罪の赦しの実感を与えられる。
〇 主日礼拝 毎週日曜日 午前10時30分から。徳島市南田宮1丁目の集会所とオンライン併用。
以下は、天宝堂集会と、第四火曜日の北島集会は対面とオンライン併用。海陽集会はオンライン(スカイプによる)集会。参加希望の方は、吉村まで連絡ください。
〇 夕拝…毎月第一、第三火曜日夜7時30分~9時
〇 家庭集会
① 天宝堂集会…毎月第二金曜日 午後8時~9時30分
② 北島集会…・戸川宅にて(対面とオンライン併用) 第四火曜日13時~14時半
・第二月曜日 午後1時~
③ 海陽集会…毎月第二火曜日 午前10時~12時
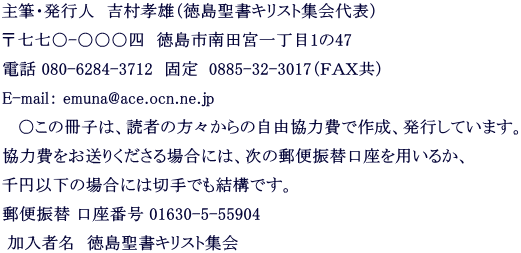
〇http://pistis.jp (「徳島聖書キリスト集会」で検索)